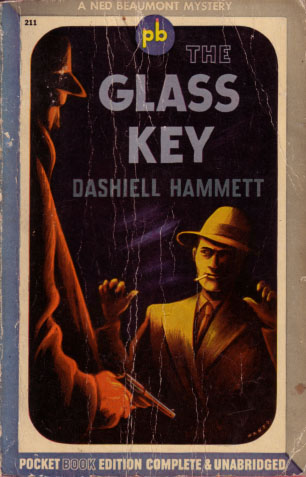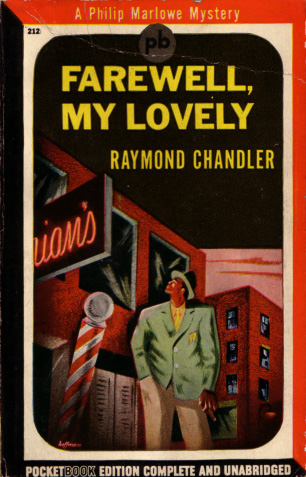ペーパーバックの倉庫から⑦
2012.09.28
ダシール・ハメットのThe Thin Manが掲載された〈アメリカのパルプ雑誌、Redbook〉。ワタシはてっきりそう思い込んでいたし、このブログでもこれまでそう書いてきたのだけれど――労を惜しまず調べてみるもんだね、何とこの「赤い本」、1903年創刊という由緒正しき女性誌。しかも、創刊以来、110年近くが経過した現在も健在。しかもしかも、現在の版元であるハーストコーポレーション(Hearst Corporation)の傘下にはわが日本の老舗女性誌『婦人画報』を刊行する「ハースト婦人画報社」も(2011年6月、ハーストコーポレーションが当時の『婦人画報』の版元であるラガルデールSCAの国外雑誌事業を買収、その一環でラガルデールSCAの子会社だった「アシェット婦人画報社」もハーストの傘下に入った――という経過らしい。詳しくはプレスリリース参照)。つまり、Redbookと『婦人画報』は今や姉妹誌。そうなると、喩えて言うならばだ、The Thin ManのRedbookへの掲載とは、大藪春彦が『婦人画報』に載ったようなもの⁉
と、大いに驚きつつも、これで少しばかり合点が行った面もある。というのは、The Thin ManはRedbookへの掲載に当って編集部による改竄が行われたことが知られていて、実はハメットサイドとしては――つーか、有り体に言えば、当時、ハメットの代理人だったBen Wassonとしてはそれでもいいと。それでもいいからとにかく原稿を売りたいと。その一連の経緯をShadow Man: The Life of Dashiell Hammett by Richard Laymanから引けば――
The novel was completed by May 1933, and Wasson began circulating the typescript to magazine publishers to solicit serial publication. The responses were disappointing. Most magazines refused to publish The Thin Man because they considered it amoral if not immoral. After two months of circulating the novel, Wasson sold it to Redbook for $5,000. The contract permitted them to publish before book publication and to include The Thin Man in a give-away volume called Six Redbook Novels, used as a premium for new subscribers to the magazine. They were also allowed by contract to condense and bowdlerize the text, which they did with a free editorial hand. The Thin Man was in the December 1933 issue of Redbook, and on January 8, 1934, Knopf published the novel, complete and unexpurgated.
で、これまたよく知られている事実ではあるし、このブログでも書いたコトがあるのだけれど、ハメットサイドから「煮て喰おうが焼いて喰おうが好きにして構わない」とのお墨付きを得た(?)Redbook編集部がやったbowdlerize(リーダーズによれば「〈著作物〉の不穏当[野卑]な部分を削除修正する」)のひとつが――
"So am I. Tell me something, Nick. Tell me the truth: when you were wrestling with Mimi, didn't you have an erection?"
というNoraのセリフを“didn't you get excited?”と改めること。まあ、Erections, Ejaculations, Exhibitions, and General Tales of Ordinary Madness(by Charles Bukowski)なんてタイトルの本まで世に存在したコトを知る後世の本読みからすれば、勃●くらい、という気もするんだけどねえ。しかし、この改変、現在、ウチに在庫のあるVintage Booksの版でもそのまま踏襲されていることを思えば、やはりアメリカ社会のエスタブリッシュメントからすれば“amoral if not immoral”ということになるのかなあ。ただ、エスタブリッシュメントの評価はそうだとしても、仮にもパルプ雑誌ともあろうものが、この程度の表現でビビるとは、何たる腰抜け――と、ワタシなんかは思っていたものだ。てっきり掲載誌をBlack Maskなんかと同類のパルプ雑誌と思い込んでいたので。しかし、意外や意外、今や『婦人画報』とも姉妹誌の由緒正しき女性誌。そりゃあ、いくら何でも勃●は……だよね。こうなると、評価は一転。他誌が揃って我が身大事の安全策を取る中で敢然とリスクを取った「男前」。モチロン、陳メ(?)の辞書では「男前」と書いて「ハードボイルド」と読む……。
2012.10.01
待てよ、そうすると、Black MaskもThe Thin Manの掲載を拒否したってこと? あのパルプの親玉のような雑誌が? 「さっき、ミミともみあってたとき、あなた、勃起しなかった?」程度のセリフにビビって? どーも腑に落ちんのでShadow Man: The Life of Dashiell Hammettを読み返すなど、色々調べてみたんだ。そうすると、実は1931年という年がダシール・ハメットの作家キャリアにおけるひとつの分岐点だったことがわかってきた。この年、ハメットは新しいエージェントを雇っている。それが、前回のエントリにもご登場いただいたベン・ワッソン(Ben Wasson)という人物なのだけれど、ワッソンが抱えるクライアントのひとりにウィリアム・フォークナーがいた。ハメットはワッソンを介してフォークナーと親交を結んだそうで、大物エージェントとの契約にはこーゆー御利益(?)もある。
ともあれ、1931年にエージェントが替わった。このことがハメットの作家キャリアにどーゆー影響を及ぼしたか? 以下は、Shadow Man: The Life of Dashiell Hammettの巻末に付録として掲載されている作品目録からベン・ワッソンと契約した1931年以降、ハメットの生前に雑誌掲載されたすべての作品(書簡類を含む)の一覧――
- "On the Way." Harper's Bazaar (March 1932). Story.
- "A Man Called Spade." American Magazine (July 1932). Story.
- "Too Many Have Lived." American Magazine (October 1932). Story.
- "They Can Only Hang You Once." Collier's (November 1932). Story.
- "Woman in the Dark." Liberty (April 8, 1933, April 15, 1933, April 22, 1933). Story.
- "Night Shade." Mystery League Magazine (October 1, 1933). Story.
- "Albert Pastor at Home." Esquire (Autumn 1933). Story.
- "The Thin Man." Redbook (December 1933). Bowdlerized version of the novel.
- "Two Sharp Knives." Collier's (January 13, 1934). Story.
- "His Brother's Keeper." Collier's (February 17, 1934). Story.
- "This Little Pig." Collier's (March 24, 1934). Story.
- "Committee on Election Rights." The New Republic (October 21, 1940). Letter.
- "A Communication to All American Writers." New Masses (December 16, 1941). Public Letter.
- "The Thin Man and the Flack." Click (December 1941). Photo story.
- "Help Them Now." New Masses (May 19, 1942). Public Letter.
まず極めて作品が少ない。「長編小説連載分をふくめて六、七十編の探偵小説を一語二、三セントで売りつくしたパルプ・ライター」(小鷹信光)の面影はここにはない。そして、このコトとも関連するのだけれど、この作品目録から指摘できるもうひとつの事実――掲載誌にパルプ雑誌が一誌もない。Collier'sやEsquireは言わずと知れた高級誌、またAmerican Magazineも1904年創刊の一般誌。Redbookが今や『婦人画報』とも姉妹誌の名門女性誌とは前エントリで記した所だけれど、Harper's Bazaarも――いや、これは女性誌というよりもファッション誌と言った方がいいのかな? あとは、そう言えばハメットって共産党員だったんだよな、と思い起こさせられるThe New Republicのような政治誌。とにかく、パルプの影も形もない。一体、いつからハメットはこんな高級な作家になったんだ? と思って作品目録を子細に検討すると、逆に1930年にはBlack Maskにしか書いていない。
- "The Farewell Murder." Black Mask (February 1930). Story.
- "The Glass Key." Black Mask (March 1930). Serialization of The Glass Key.
- "The Cyclone Shot." Black Mask (April 1930). Serialization of The Glass Key.
- "Dagger Point." Black Mask (May 1930). Serialization of The Glass Key.
- "The Shattered Key." Black Mask (June 1930). Serialization of The Glass Key.
- "Behind the Black Mask." Black Mask (June 1930). Letter.
- "Death and Company." Black Mask (November 1930). Story.
ほとんど専属作家状態。それが1932年(1931年は発表作品なし)には一転――。大物エージェントの起用はハメットを高級誌の書き手にした。しかし、それはパルプ・ライターとしてのハメットのキャリアが終わったことをも意味していた。人間ダシール・ハメットは1961年に死んだ。しかし、パルプ・ライターとしてのハメットは1931年に死んでいた……。
2012.10.03
ふーむ。読みようによっては、これはなかなかに意味深……。ダシール・ハメットとレイモンド・チャンドラー。ともにBlack Maskをメインの発表媒体とするパルプ・ライターとしてミステリ作家のキャリアをスタートさせたハードボイルド派の二大巨頭というコトになるのだけれど、二人のパルプ・ライターとしてのキャリアは学校で言うならば入れ違い。ハメットが1930年11月号のDeath and CompanyでBlack Mask Schoolを“卒業”したのに対し、チャンドラーは1933年12月号のBlackmailers Don't Shootで“入学”。実年齢ではチャンドラーの方が6つばかり年上なのだけれど、Black Mask Schoolではチャンドラーはハメットの後輩ということになる。
で、単に後輩というだけでなく、この後輩は先輩を崇め、大いに模倣もした。それはチャンドラー自身が書簡等で積極的に認めているところ。1976年に刊行されたThe Life of Raymond Chandlerで著者のFrank MacShaneはチャンドラーの書簡やエッセイを縦横に引用しつつその生涯を再構成しているのだけれど、後輩チャンドラーから先輩ハメットへの“贈る言葉”とも言えるこんな下りも(引用文中、ダブルクォーテーションで括られているのがチャンドラーの書簡ないしはエッセイからの引用)――
Chandler studied Hammett's work with care, and his own grew out of it. "I did not invent the hard-boiled murder story," he wrote to a fellow crime writer, "and I have never made any secret of my opinion that Hammett deserves most or all of the credit. Everybody imitates in the beginning. What Stevenson called playing the 'sedulous ape'." (...) He admired Hammett's narrative ability and said that he'd gladly read one of his novels even if the last chapter were torn out. "It would be interesting enough without the solution," he wrote. "It would stand up by itself as a story. That's the acid test."
たとえ最終章が剥ぎ取られていようが、ハメットの小説ならオレは喜んで読むぞ。事件が未解決のままでもきっと一編のストーリーとして成立しているはずだ――なんて、先輩作家に対する褒め言葉としても、ただ謎解きだけの凡百の探偵小説に対する皮肉としても、いかにもフィリップ・マーロウの生みの親らしい。ともあれ、チャンドラーはハメットを崇拝していた。ただ――ただねえ、実はこれまではどーというコトもなく読み過ごしていたのだけれど……。
The Life of Raymond Chandlerの↑に引用した部分から5ページばかり前、チャンドラーがなぜBlack Mask Schoolに入学する気になったのかという辺り。Frank MacShaneはここでチャンドラーが1950年にイギリスの出版社、Hamish Hamiltonに送った手紙を引用しつつその経緯を明らかにしているのだけれど――
During the 1930s he read the so-called slick magazines, such as the Saturday Evening Post, Collier's, Cosmopolitan and Liberty, always in search of a vehicle for his work. But he never liked them and was put off by "their fundamental dishonesty in the matter of character and motivation." He therefore started to look elsewhere. Driving along the Pacific coast with Cissy, he would pick up pulp magazines, so-called because they were made from wood pulp, in order to have something to read at night. He liked them "because they were cheap enough to throw away and because I never had any time for the thing which is known as women's magazines." With the need to publish becoming increasingly evident Chandler had a thought: "It suddenly struck me that I might be able to write this stuff and get paid while I was learning."
この当時のチャンドラーはというと、副社長まで務めた石油会社(ダブニー石油シンジケート)を馘首(1932年)、妻(Cissy。18歳年上の姉さん女房)も抱える身でこの上は筆で身を立てるしかないと思い定めていた頃。最初はスリックへの投稿を考えあれこれ読み漁るも、登場人物その他どーにも空々しくて馴染めない。で、安いし、女性誌みたいなのは論外だし、というコトで、パルプ雑誌で憂さを晴らしていたのだけれど、ある時、卒然として思い至った、これならオレにも書けるんじゃないか……。ま、そんな感じ。特段、驚くようなエピソードが明かされているわけではない。ただ――1932年という年に注目。10月1日付けエントリでも記したように、この年、ハメットはパルプ・ライターから足を洗ってスリックの書き手に転身。チャンドラーが“fundamental dishonesty”に辟易したCollier'sやLibertyにも寄稿。そしてチャンドラー言うところの“which is known as women's magazines”そのものであるRedbookやHarper's Bazaarにも。ふーむ。読みようによっては、これはなかなかに意味深……。
2012.10.09
ふむ、相手も同じ赤門出身。しかも、自分より20歳近くも年上。当然、遠慮もあっただろうし……。
いや、なに、丸谷才一はかの有名なフィリップ・マーロウの名台詞――「しっかりしていなかったら、生きていられない。優しくなれなかったら、生きている資格がない」(清水俊二訳)の訳文についてはどう思っていたのだろうと考えていたら、ついそんなことをね。一応、後段の「優しくなれなかったら、生きている資格がない」については「角川映画とチャンドラーの奇妙な関係」(『夜明けのおやすみ』所収)で「清水俊二ふうに訳すのが正しい」とはしているんだけど……。
そもそもこのフィリップ・マーロウの台詞を世に知らしめしたのが丸谷才一。1962年、この希代の名文家は当時、『エラリイ・クイーンズ・ミステリ・マガジン』に持っていた連載「マイ・スィン」でこう書いた――
ここには、タフな行動人と瀟洒なサロンの社交人とを一身に兼ね備えた男がゐる。事実、マーロウは、「あなたのようにしっかりした男がどうしてそんなに優しくなれるの?」と女に訊ねられたとき、かう答えるのである。
「しっかりしていなかったら、生きていられない。優しくなれなかったら、生きている資格がない」
この箴言には、ラ・ロシュフーコーのやうな苦さはないだらう。また、ニーチェのやうな厳しさもないだらう。しかし、独特の、甘美で爽やかな味はひがある。
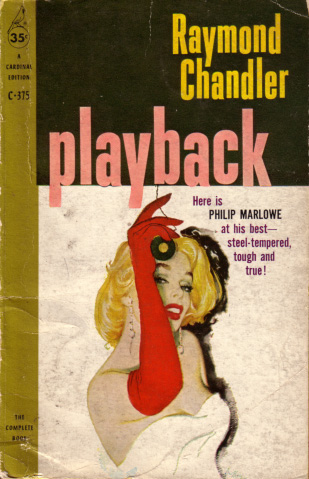
実はこの名台詞はこうして丸谷才一が取り上げるまで世間ではほとんど注目されていなかったという。このことは丸谷才一自身が明言していて、「このマーロウの台詞も、わたしが名せりふだと指摘する前は別に大向うをうならせてはゐなかつたもので、つまり誰も注目してゐなかつた」(「角川映画とチャンドラーの奇妙な関係」)。実際、この小説について書かれたWikipedia英語版の記事を見てもこの台詞については一言も触れられていない。まさにこの台詞は丸谷才一の指摘によってはじめて名台詞になったのだ。さしずめ丸谷才一という“目利き”によって骨董市で掘り出された名刀みたいなもの。ただ、その名刀の切れ味がどうも……。
結局、ポケミス版『プレイバック』における清水俊二訳がどーも食い足りんのだ。もっとうまく訳せるはず。煎じ詰めればhardの訳し方なのだろうけど、「しっかり」はないわ。だって「しっかり」と「やさしい」ってフツーに共存可能。「しっかり」ものの「やさしい」母さんとか(笑)。ここは本来、相反する属性が一つの人格の中に共存するというパラドックスが語られているワケだから。それならばとオノレの貧しいボキャブラリーの中からなけなしの形容詞を引っぱり出してはあれこれ当て嵌めてみるのだけれど、どーも。やってみてわかかるのだけれど、hardってこんなに訳すのがハードな単語だったのかと。訳すのがハードな割には、言わんとするところを理解するのはむしろイージー。それだけに、これでもない、これも違うと。遂には(少なくともこの文脈では)hardを日本語に置き換えるって無理なんじゃないのかと。実際、矢作俊彦は「夢を獲える檻」(『複雑な彼女と単純な場所』所収)でこんな訳を披露しているくらい――
ハードでなければ生きていけない。ジェントルでなければ生きて行く気にもなれない。
ただ、「ハード」ばかりか「ジェントル」もそのままというのはなあ。普通、言わないもん、日常会話で「ジェントル」なんて(一応、「騎士道に範を置く単語」だから訳せないというコトらしい)。あと、生島治郎が『傷痕の街』のあとがきでこんな訳を披露しているんだけど――
タフじゃなくては生きていけない。やさしくなくては、生きている資格はない。
これをのちに角川映画がパクって問題になったわけですね。「角川映画とチャンドラーの奇妙な関係」はこのことについて書いている。で、言わんとすることは重々理解できるんだけど、ただ「タフ」はそれこそtoughのカタカナ訳で、それをhardの訳語に当てるというのはねえ……。
――というような次第で、清水俊二訳も含め、これというようなものは。せっかくの名台詞なのに、それにふさわしい名訳(定訳)がないとは、何ともモドカシイ限り。どうせなら掘り出した責任で丸谷才一が訳しておいてくれればよかったのに。丸谷才一自身、東京大学文学部英文科で修士号まで取得した英文学の専門家。ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ』など翻訳の仕事も多い。当然、フィリップ・マーロウの名台詞についても自分なりの訳があったと思うのだけど、でもそうすると赤門の先輩に対するダメ出しということになるしなあ。それを慮ったのか……と、冒頭の述懐に戻るわけなんだけど――
ただ、もしかしたらこのフレーズに関しては、こんなふうにあれこれ翻訳に拘ること自体、意味がないのかも。というのも、このフレーズ、原文が、もう――
If I wasn't hard, I wouldn't be alive. If I couldn't ever be gentle, I wouldn't deserve to be alive.
何という奥行きのある……。改めて説明するまでもないと思うけど、全文、仮定法過去。つまり、事実に反する仮定。事実に反する仮定が↑のようなものであるということは、翻って言えば、事実がいかなるものであるかもこの一節によって語られているということ。しかも、一人称でそれがなされているということは、自分語り。本来、それって相当に恥ずかしいことだと思うのだけど、仮定法過去という晦渋なレトリックで包むことで大人が口にするに耐え得る台詞にしている。さらに言えば、後段のcouldn't。これがあることによって表現にグーンと深みが増している。可能の助動詞がここに来るということは、gentleは努力目標なんだよね。hardは所与だが、gentleは努力目標。そんなことがさり気なく歌い込まれている(丸谷才一が「清水俊二ふうに訳すのが正しい」としているのも、このcouldn'tのニュアンスをめぐって)。これは、深いよ。もうこの期に及んでhardの訳語がどうの、gentleの訳語がどうのと、ちまちま言葉を捏ねくり回すことに何の意味がある。レイモンド・チャンドラーによって書かれ、丸谷才一によって掘り出された名台詞はただ原文のまま、あるがままに鑑賞されるがよろし……。
About Me
On PW_PLUS
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②
- ◦そのぷろふいる、偏見につき〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜
- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜
- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜