よく熟慮された親切という奥ゆかしい行動
かのジャパン・ガゼットの発行人兼編集人だったJ・R・ブラックが晩年になって書き下ろした『ヤング・ジャパン 横浜と江戸』は興味深いエピソードがてんこ盛り。ワタシも『「東武皇帝」即位説の真相 もしくはあてどないペーパー・ディテクティヴの軌跡』の参考資料として大いに活用させてもらったのだけど、ここではこんな一節を紹介したい。1865年のとある日というからまだ彼がジャパン・ヘラルドにいた頃の話。1人の「若い日本人紳士」がジャパン・ヘラルドの編集部を訪ねて来たという――
私を訪問して来た紳士は、当時大変若かった。彼は、外国語学校の一つに通っていた。同僚達とともに、外国人の指導を受けて、軍事教練も受けていた。
極めて控え目に、彼は「無礼を許して下さい」と願い、「誰にも、あなたを訪ねたことを洩らさないでほしい」と述べた。それから次のように話した――役人(彼の藩の者と私は了解したが)から命令を受けて、私に会見し、前年の八月にフランスで使命を失敗したために、江戸で幽閉された使節は、今もって監禁されている、さらにこのことを新聞に書き、「釈放されて然るべきだ」という勧告を載せてもらいたい、と求めに来た――と。
私は確かに要求には応じると答えた。そして彼の訪問を秘密にしておくこと、したがってこのことについて、なんら懸念には及ばない、と請け合った。
したがって、本件を、次の土曜日(一八六五年〔慶応元年〕六月二十四日)の社説の主題にしたが、それ以上は、何か聞けるとは予期していなかった。もし私の記憶が正しければ、当時この新聞の日本人の購読数はわずか六部ほどにすぎなかった。
その記事が載ってのち、どのくらい時間がたったか覚えていないが、また同人の訪問を受けた。その目的は、私に感謝し、外国新聞紙上の訴えは成功したことを話すためであった。(ねず・まさし、小池晴子訳)
まずここに出てくる「江戸で幽閉された使節」なんだけど、文久3年に第2回遣欧使節、いわゆる「横浜鎖港談判使節団」を率いて訪欧した池田長発と考えて間違いない。備中国井原を知行地とする旗本で、最近ではそのイケメンぶりが盛んに取り沙汰されており、「まるで渋谷でブレイクダンスでもしていそうな雰囲気」との評言も(「古典的な美しさを11人の侍から振り返ろう」参照)。また小田井蔵太とともに彰義隊の頭を務めていた池田長裕とは叔父・甥の間柄。慶応4年当時、甥が示したほどの徳川への忠誠心を叔父が持っていたかは……まあ、この辺は措いておこう。
それにしても「幽閉」だの「監禁」だの、穏当ではない。一体どういうことなのか? 実は池田長発は帰国後、ミッション失敗の責任を問われて知行高半減、蟄居謹慎という厳罰処分を科せられているのだ。まあ、ミッション失敗と言ったって、そもそも「鎖港談判」というミッションが無理筋だったのだが。なにしろ一旦開いた港をまたぞろ閉じたいというのだから。そんなの、西洋列強が受け容れるはずがない。しかし孝明天皇は文久3年5月10日をもって攘夷の勅命を発しており、幕府としても何かしらそれに類した行動を取らざるをえない。で、苦肉の策として打ち出したのが一旦開いた港を閉鎖する――というか、そのための交渉を西洋列強とはじめるという方針。もちろん幕府としてもそんな要求が通るとは思っていないのだが、しかし交渉することならできる。で、朝廷には現在、鋭意交渉中であるということにしてとりあえず時間を稼ぐ――と、もう本当に苦肉の策と言うしかない。当然、幕府の本音としては談判の正否なんて二の次。ゆっくりと1、2年はヨーロッパを歴訪して時間を稼いでくれればというのが本音。
ところが、あろうことか池田長発はわずか7か月で日本に帰ってきてしまう。しかも横浜港の鎖港という本来のミッションとは真逆の内容を含む4か条からなる「パリ約定」に調印までして。まあ、「パリ約定」に調印したことについてはフランス側の交渉相手である外相のドリュアン・ド・リュイスにいいように転がされたという側面があったらしい。なにしろドリュアン・ド・リュイスはこの時、58歳。一方の池田長発は27歳。ドリュアン・ド・リュイスからするならば赤児の手を捻るようなものだったろう。
ただ、「パリ約定」の調印をもってすべての日程を切り上げ、急ぎ帰国することにしたのにはそれなりの理由があったらしい。これについて一般には西洋の実情に触れ、開国の不可避を悟ったため――とされているのだけど、東京大学史料編纂所が所蔵する「甲鐡艦収領顚末」という史料には少しばかり異なる理由が記されていて、それによれば池田長発がフランスから急遽帰国したのは、フランスが軍事力を背景に長州を「問罪」しようとする方針であることを知り、急ぎ「危急ヲ報シ政府ノ処置ヲ仰グ」ためだったという。確かに一行は「パリ約定」の調印を終えるや直ちにイギリス、オランダの両国に帰国挨拶状を送付し調印翌日の5月17日(和暦。年号は元治と改元)には早々にパリを出発している。もし「甲鐡艦収領顚末」が記すような理由だったとすれば、このあまりにも迅速な行動も腑に落ちる――とは言える。
ともあれ、かくて一行は予定を大幅に早め、7月17日には横浜に帰ってきてしまう。この想定外の事態に幕府はどう対応したか? 使節団に筆頭随行員として同行した田辺太一が明治31年に刊行した『幕末外交談』によれば――「然るに其七月十七日、使節の船、横濱に着せしの報あるや、幕府は大に驚き、其歸朝の理由を問ふにも及ばず、陸續外國奉行、目付等を差し來らしめ、其上陸を止め、或は暫時上海なり香港なりその跡を潛めよ、との訓令を傳ふるにいたり」云々。ほとんど三谷幸喜ワールド? しかし一方の池田長発は必死ですよ。なにしろ、そもそもの帰国の理由が「危急ヲ報シ政府ノ処置ヲ仰グ」ためだったというんだから。で、周囲が止めるのも聞かずに単身、江戸に向かった。もしそのままだったら「押懸登城」ということにもなりかねなかったんだけど、それだけは後を追いかけてきた副使の河津祐邦、目付の河田熙に説得されて思い止ったようだ。しかし、池田長発はその日のうちにお役御免。さらには知行高半減、蟄居謹慎という厳罰処分を科されることになる。
――と、ことここに至る事情を呑み込んでいただいたところで、次は「若い日本人紳士」の求めに応じてJ・R・ブラックが書いた社説を紹介しよう。幸いにもジャパン・ヘラルドの1865年6月24日号は現存しており、ぺりかん社刊『日本初期新聞全集』編年複製版第6巻に収録されている。それは次のようなものだった――
すべての文明国においては、男性、ことに上流階級の男性は彼らの個人的権利を守ることに汲々とし、またしきりに自身の影響力とパワーを高めようとするのが相場である。かくて誰も他人の権利や、幸運にしろ悪運にしろ、他人の運命に思いを馳せることはない――それが彼ら自身に直接の影響がない限り。さて、ここで話は1863年にヨーロッパに行き、パリに短期滞在した後、昨年7月に日本に帰ってきた日本の使節団についてだ。彼らのミッションは政府により失敗だったと見なされ、収監された。彼らは今日に至るも依然、拘禁されたままだ。そして誰も彼らにそれ以上の考えを及ばそうとはしない。
現に大君政府がそうであると証明しつつあるような開明的なものたちにとっては、能力の限り誠実に奉仕するものを取り扱うそのような態度がすべての西側諸国の市民から非難を受けるのは当然のことだと理解できるはずだ。われわれは日本の最高級官僚にとってさえ失敗による非難や恥辱に甘んじるよりも自殺を選ぶことが慣習であることを知っている。しかしそういう考え方はより時代精神と調和する何かに取って代わられるべきであり、また騎士道的な観念は常識というより素朴で実用的な知恵に従うべきである。「真摯に世界に奉仕することは世界を支配することよりも遙かに偉大である」とラマルティーヌは言った。そして正しい心を持ったすべてのものは必ずや己の義務を精力的に果そうとするものを称賛するはずである、たとえ彼が成し遂げようとした目的が達成できなかったとしても。
先の使節団がヨーロッパに行った時、彼らは自分たちが失敗するであろうことを知っていた。それでも彼らは最善の努力を尽して彼らのミッションの目的を達成することを決意していた。彼らは失敗には処罰が待ち受けていることを十分に承知していた。それでも彼らは「世界がわれわれの心に何らかの疑念があるかのように思わせてはならないし、だからこそ大君の書簡が馬鹿げていると受け取られるようなことはあってはならない」と考えた。そしてできる限りのことをやった。その上で彼らは「日本に帰り、政府にヨーロッパの実情を知らしめるのが適当である」と考えた。
彼らの帰国と時を同じくして連合艦隊が下関に向け出撃しようとしていた。彼らの帰国の最初の影響はこの出撃を暫時、見合せるというかたちで現れた。しかし彼らがパリで調印したいわゆる「条約」なるものは政府から承認されず、彼らは逮捕拘禁されたことがすぐに明らかになった。彼らが咎を受けてから10か月が経った。そして彼らの処罰が、もし彼らのために行使されれば効果を発揮するかもしれない影響力を持っているものの関心を引くこともなくなった。
われわれは、それゆえ、大君と彼の政府に以下のことを訴えたい。
使節団に科せられている刑はあまりにも苛酷であまりにも恣意的である。刑の取り消しは、あなた方が推進したいと望んでいる進歩政策の一部となるであろう。
使節団は逮捕されたが、彼らの「条約」の大部分は実行されたか、実行されつつある。あの条約に含まれた条項、たとえば――
「横浜は鎖港しない」
「日本人と外国人の友好は、条約国ばかりではなく、すべての外国人との間で維持する」
「商業は自由であるべきである」
「すべての外国人の財産は尊重されるべきである」
「日本人学生をヨーロッパに派遣して指導を受けることを検討する」
そして――
「外交官ならびに経済界の代表をヨーロッパに派遣することを検討する」
これらのすべての合意は今なお有効であり、日本政府の一部にはこれらに従って行動しようという意向も見受けられる。ヨーロッパでは国家のために誠実に努力した臣民を投獄したりその他の方法で罰する君主は絶対的な劫罰に晒されることになる。彼は暴君として烙印を押され、その名前は物笑いの種になる。その一方で受難者は殉教者と見なされることになる。
かくて、ことは至って明白である。大君は失敗の処罰という古い指針に代わって成功の報酬という指針を切り開くことで、世界の評価においていかに多くのものを得るかを知ることになるだろう。いずれにしても、使節団は既に十分な期間、処罰を受けた。もし条約国の代表がその影響力を彼らの釈放のために行使するなら、それはよく熟慮された親切という奥ゆかしい行動となるだろう。
実に格調高い。「近代日本ジャーナリズムの父」(『英文毎日』の編集者などを務めた花園兼定が1926年に刊行したJournalism in Japan and Its Early Pioneersで用いた表現)とも称されるJ・R・ブラックのジャーナリストとしての力量が十分にうかがえる内容。全文が邦訳されるのは、もしかしたら本邦初? 原文の格調が損なわれていなければいいのだけど……。ともあれ、こうして「よく熟慮された」筆致で綴られた社説はジャパン・ヘラルドの1865年6月24日号の紙面を飾った。そして件の「若い日本人紳士」が再びジャパン・ヘラルドのオフィスを訪れ「外国新聞紙上の訴えは成功した」と報告したということは、もしかしたらこの社説を読んで実際に「影響力」を行使した公使なり何なりがいたということなのかもしれない。いやー、すごい話ですよ。だって、まだ慶応年間ですよ。そんな時代に新聞が政治を動かしたのだ。時代は間違いなく「明治」へと進んでいた――ということかなあ。
それにしても、この「若い日本人紳士」、一体誰だろう? おそらくは使節団の一員ではないかと思うんだけど。ヒントは「彼は、外国語学校の一つに通っていた。同僚達とともに、外国人の指導を受けて、軍事教練も受けていた」という記述。さらには「今では、外国人からも、日本人からも、高く評価されている、非常に勢力のある人物だ」とも記されていて、これらの情報から該当する人物を求めるなら……益田孝はどうだろう? 益田孝は父・益田鷹之助とともに「通弁御用当分御雇」として使節団に参加。帰国後は横浜でイギリス駐留軍の士官に就いて軍事教練を受けていた。「実は英語が覚えたいのだが、英語を教えてくれと言うたのでは教えてくれないから、調練をやったのである」(『自叙益田孝翁伝』)。また同書には「ヘボン塾」に通っていたことも記されていて、「ヘボン塾」を外国語学校と見なすなら「外国語学校の一つに通っていた」という条件にも合致。そしてJ・R・ブラックが『ヤング・ジャパン』を執筆していた明治13年当時は三井物産社長。まさに「外国人からも、日本人からも、高く評価されている、非常に勢力のある人物だ」。
もっとも当の益田孝は『自叙益田孝翁伝』で池田長発(官名は筑後守)の帰国後の処遇について――「筑後守は、帰朝したら余程重いお咎めがあろうと心配しておったのだが、大したことはなかった。しかし神奈川から内へ入ることは許されなかった」。まるで丸2年に及ぶ蟄居謹慎などなかったかのような口ぶり。あるいはそれは「鈍翁」と号した数奇者ならではのおとぼけ……?
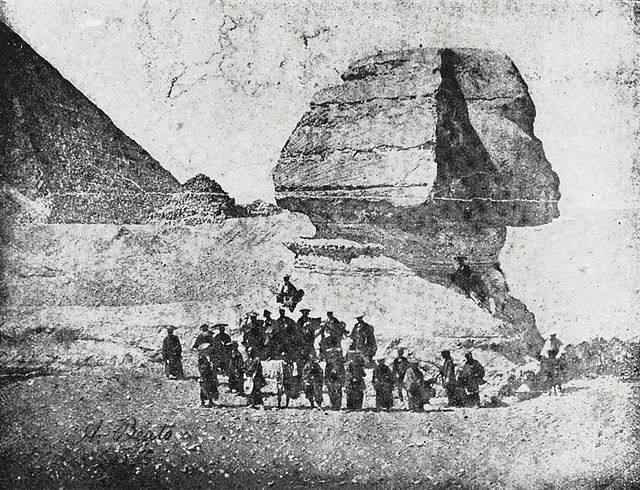
About Me
On PW_PLUS
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②
- ◦そのぷろふいる、偏見につき〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜
- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜
- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜
