小沢一郎と『山猫』
本稿は2008年にブログ記事として公開したものです。本サイトに再録するに当って、一部内容を修正しています。
話は11月2日に遡る。この日は、1963年にカンヌ映画祭でパルム・ドールを受賞した『山猫』や1974年の『家族の肖像』で名コンビぶりを発揮したイタリア人映画監督ルキノ・ヴィスコンティとアメリカ人俳優バート・ランカスターの共通の誕生日(ヴィスコンティの方が七つばかり年上)。同日付けの産経新聞のウェブサイトMSN産経ニュースは「次代への名言」と題するコーナーでこの事実に触れた上で、バート・ランカスターが『山猫』の中で口にした(とされる)セリフ――「変わらずに生き残るためには変わらなければならない」を取り上げている。
このセリフ、同コラムでも述べられているように、民主党の小沢一郎代表が2006年4月の代表選の際に「政見演説」(投票前に行われた決意表明のようなもの)の締め括りで、言わば“決めセリフ”よろしく引用、勝利を決定づけたとされる曰く付きのもの。以下、その一節を紹介すると――
最後に、私はいま、青年時代に見た映画『山猫』のクライマックスの台詞を思い出しております。イタリア統一革命に身を投じた甥を支援している名門の公爵に、ある人が「あなたのような方がなぜ革命軍を支援するのですか」とたずねました。バート・ランカスターの演じる老貴族は静かに答えます。
「変わらずに生き残るためには、自ら変わらなければならない(We must change to remain the same.)」
確かに、人類の歴史上、長期にわたって生き残った国は、例外なく自己改革の努力を続けました。
そうなのだと思います。よりよい明日のために、かけがえのない子供たちのために、私自身を、そして民主党を改革しなければならないのです。
ところが、ご丁寧にも英文まで添えて引用された“決めセリフ”ではあるのだけれど、MSN産経ニュース「次代への名言」によるならば「字幕を見る限り、イタリア語版でも英語版でも公爵はそんなことは言っていない」。映画の前半、アラン・ドロンが演じる「魅力的だが、政治的にはやや無節操な公爵のおい」がそれに近いセリフを口にする場面はあるものの、公爵その人については「革命や変化に違和感(嫌悪感に近いかもしれない)を抱き、隠棲(いんせい)の道を選ぶ人物として描かれている」。
実は、これに類する指摘は他にもあって、2006年5月8日付け毎日新聞「発信箱」では「山猫は変わらない」(署名は編集局・山田孝男氏。ちなみに、「次代への名言」で「他紙の政治コラム」としているのはおそらくはこれ)と題してこう記している――
名匠ルキノ・ビスコンティの「山猫」は1963年カンヌ映画祭グランプリ受賞作である。舞台は19世紀半ばのイタリア南部シチリア。革命に身を投じた青年(アラン・ドロン)が伯父ドン・ファブリツィオ公爵(バート・ランカスター)に「生き残るために変わらねば」と迫るが、公爵は取り合わない。
一方、小沢氏の説明はこうだ。「青年時代に見た映画『山猫』のクライマックスで、イタリア統一革命に身を投じた青年が伯父の公爵に『なぜ革命軍を支援するのか』と尋ね、バート・ランカスターの老貴族が『生き残るために変わらねば』と答えた」――。
セリフの主客が逆だ。それにこの場面は山場ではなく、開幕早々に現れる。公爵は愛するおいに財産の一部を与えるが、「私も変わる」などとは言わない。自らは変化を拒み、誇り高く滅び去る。山猫とは公爵家の紋章だ。映画の主題は変革ではなく、貴族階級の落日なのである。
うーん、ここまで言われては、小沢サンとしても黙ってはいられないはず。当然、何らかの反論が寄せられたに違いないと思いきや、前述「次代への名言」によれば「残念なことに、期待していた小沢代表からの反応(反論)はいまもない、という」。一体どういうこと? ひょっとして、産経・毎日両紙の指摘は事実なんだろうか? それとも、とかく「言い訳をしないが、説明もしない」などと揶揄されがちな“小沢流”を貫いているだけ……?
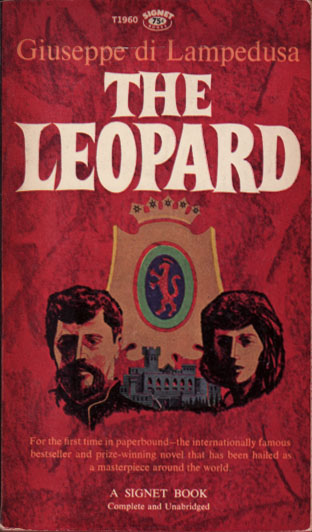
ともあれ、その映画『山猫』は1963年、イタリア・フランスの合作映画として制作。原作はジュゼッペ・トマージ・ディ・ランペドゥーサの同名小説(→は1961年刊行のSignet Booksの版)。本国イタリアでは当然、イタリア語版が公開されたわけだけれど、アメリカや日本ではセリフをすべて英語に吹き替えた「国際版」として公開(日本公開は1964年)。イタリア貴族が英語を喋るというなんとも面妖なシロモノ(ただし、アメリカ人俳優であるバート・ランカスターのセリフは本人の声。アラン・ドロン、クラウディア・カルディナーレ等、その他のキャストはアメリカ人声優による吹き替え。一方、イタリア語版では逆にバート・ランカスターの声がイタリア人声優による吹き替え。何を以て「オリジナル」とするかはなかなかに微妙?)。しかも、この「国際版」、配給元の20世紀フォックスによって205分あったオリジナルは161分に短縮。しかし、完全主義者として知られるヴィスコンティがこんな仕打ちをよしとするはずもなく、1981年、自らの手で185分に再編集した「オリジナル完全版」を公開。日本では岩波ホールがエキプ・ド・シネマ第44回ロードショーとして上映(ちなみに、ワタシが『山猫』をはじめて見たのもこの岩波ホールの「オリジナル完全版」)。ただ、この「オリジナル完全版」もベースとなったフィルムの保存状態が良くなく、大幅な褪色が認められるという欠点が。それを最新のデジタル技術を駆使して復元した「イタリア語・完全復元版」が初公開からちょうど40年となる2004年に公開(ちなみに、ワタシは劇場では見ておりませんが、DVDを持っております)。
つまり、『山猫』にはざっと3つのバージョンがあるわけだけれど、現在、レンタルビデオ店で借りることができるのは「国際版」。そして、毎日・山田コラムはこの「国際版」を元としているようなので、本稿でもまずはこの英語吹き替え版を再生することにしよう。すると、冒頭、次のような字幕が表示される――
In 1860, Italy was thrown into a political and social upheaval by a man called Garibaldi. He sought to unify Italy into a modern nation freeing it from domination by a decadent aristocracy.
Caught in this turmoil was a proud Sicilian prince known as The Leopard. This is his story and that of his family, his way of life and his credo:
“Things will have to changein order that they remain the same.”
小沢一郎サンが政見演説において引用した「変わらずに生き残るためには、自ら変わらなければならない(We must change to remain the same.)」とは、言い回しは若干異なるものの、意味するところは同じ(小沢サン自身はあるインタビューで「あのフレーズがそのまま出てくるわけじゃないけど、似たようなことを言っているんだ」と説明)。字幕ではそれをドン・ファブリツィオの「信条」として紹介しているわけだから、なんだ、やっぱり小沢サンが言っていることは正しかった?
しかし、この冒頭の字幕は国際版でのみ表示されるもの。国際版はシドニー・ポラック監修の下に制作されたとされるのだけれど、この映画が時代背景とするイタリアの「リソルジメント(統一)」が一般には馴染みが薄いとの配慮から付け加えられたものと思われる。ただ、それに留まらず〈Things will have to change in order that they remain the same.〉なるフレーズを引いた上でそれを公爵の「信条」としているのは、これまた19世紀イタリア貴族社会といういささかとっつきにくい世界に観客を誘い込むための「口上」――言わばシドニー・ポラックなりのサービス? しかし、いささかサービス過剰の嫌いも。なぜなら、実際に公爵が上記の如き逆説を自らの「信条」としているかどうかは、映画を見終わった後も一概には判断できないというのが実情なのだから。実際、わが国では、産経・毎日といった大手メディアが声を揃えて「そんなことは言っていない」と指摘しているくらい。
ともあれ、産経・毎日両紙が問題にしているのは、小沢サンが「バート・ランカスターの演じる老貴族は静かに答えます」としている点。である以上、冒頭の字幕はこの際、脇に置くべき。そもそもこの「国際版」、イタリア貴族が英語を話すという面妖さにどうしても違和感を拭えない上にはたして英訳としても適訳と言えるのかどうか。字幕で公爵の「信条」とされているフレーズは、この後、登場する公爵の甥のセリフ(If we want things to stay as they are, things will have to change)を客観化したものとも考えられるのだけれど、訳は1960年初刊となるアーチボールド・コルクハウン(Archibald Colquhoun)による英訳を踏まえたもの。しかし、何とも回りくどい言い回し。それにひきかえ、「イタリア語・完全復元版」の場合は不自然な吹き替えに興醒めさせられることもない上に表示される英語スーパーもずっとシンプル。よって、以後、この小文では基本的にこの「イタリア語・完全復元版」を踏まえつつ、引用に当っては1981年に岩波ホールで上映された「オリジナル完全版」の劇場パンフレットに収録されている「採録シナリオ」(翻訳/監修・清水馨)を使用することに(本当ならば映画の場面そのものを引用したいところなんだけど、著作権法上、それは無理なようなので)。
ということで、まず問題となるのは、この場面――
● サリーナ邸・公爵の居室
鏡にむかい,髭をあたっている公爵.その鏡の中にいかにも清々しい若者の顔が映る.甥のタンクレディだ.
タンクレディ「おはよう,叔父上!」
公爵「タンクレディか! 昨夜は何をしていた?」
タンクレディ「昨夜? 何もしてませんよ.友だちといましたが清遊です.誰かのように,パレルモで夜遊びなどしませんよ」
公爵「誰かとはだれだね?」
タンクレディ「とぼけないで下さい.アイロルディの検問所で軍曹と話しているのをこの眼で見ましたよ.年甲斐もなく! おまけに神父まで連れて! 浮気な道楽者!」
公爵「まあ……その通りだ.ミミ!(と召使いを呼んでから,再びタンクレディに)その格好は一体何だ? 朝から仮装舞踏会か?」
タンクレディ「あと1時間ほどで出発します.だから,お別れを言いに来ました」
公爵「何だと? どこへ行くのだ? 決闘にか……」
タンクレディ「そうです.ナポリ王との大決闘に行くんです.フィクッツァの陣営に参加します.こんな時にじっとしてなどいられませんよ.大変革の時なんですから」
公爵「気でも狂ったのか.奴らはみんなマフィアだ,ぺてん師だぞ.ファルコネーリ家の一員であるおまえは,王のために我らとともにあるべきだ」
タンクレディ「王のために? どの王です? 前王ならともかく,今のフランチェスコ王では話にならない.とても駄目ですよ」
公爵「ピエモンテの“誠実な男”と呼ばれている,あの王の方がましだと言うのか? ナポリ方言がピエモンテ方言に変わるだけではないか」
タンクレディ「では,マッツィーニのいう共和制になってもいいんですか?……信じて下さい,叔父上.もし僕らが参加しなければ,彼らはまちがいなく共和制にしてしまう.現状維持を願うなら,全てを変えねばならないのです.分って下さいましたか? では,叔父上,三色旗を持って戻ってきますよ」
産経や毎日のコラムで指摘しているのがこのシーンなのは明らかなんだけど、確かに「主客は逆」。この後、「三色旗を持って戻ってきますよ」と述べるアラン・ドロン演じるタンクレディに対して「三色旗か! 口を開けば三色旗というが、我らの金色の百合の旗に比べてみろ。あんな色の寄せ集めなど何の役に立つ?」と毒づくなど「公爵は取り合わない」。その後、立ち去ろうとするタンクレディを呼び止め「ロトリーノ(金貨をつめた円筒形の袋)」を手渡すのは「革命軍を支援する」行為と言えなくもないが、むしろ甥に対するささやかな餞別と見るのが正解――と、このシーンを見る限りでは、小沢サンが言うような「自己改革の努力」というメッセージを読みとるのはなかなか難しい。
しかし、まだ映画は始まったばかり。きっと小沢サンの言う通り、この映画の「クライマックス」でそれこそ「決めセリフ」よろしく件のセリフが飛び出すに違いない――。さて、果たして「山猫」は小沢サンが述べたようなセリフを口にするのかどうか? 答えは、YESであり、かつNO……。
2006年4月、いわゆる「堀江メール問題」によって大混乱(「国際版」の冒頭の字幕で言うところのturmoilだね)に陥った民主党がその危機乗り切りの舵取り役を選ぶべく実施した代表選に際して小沢一郎サンが披瀝した「政見演説」の“決めセリフ”。その一節をここで改めて引くと――
最後に、私はいま、青年時代に見た映画『山猫』のクライマックスの台詞を思い出しております。イタリア統一革命に身を投じた甥を支援している名門の公爵に、ある人が「あなたのような方がなぜ革命軍を支援するのですか」とたずねました。バート・ランカスターの演じる老貴族は静かに答えます。
「変わらずに生き残るためには、自ら変わらなければならない(We must change to remain the same.)」
これに対し、毎日新聞編集委員・山田孝男氏がコラム「山猫は変わらない」で指摘した事実関係にまつわる疑義――
一方、小沢氏の説明はこうだ。「青年時代に見た映画『山猫』のクライマックスで、イタリア統一革命に身を投じた青年が伯父の公爵に『なぜ革命軍を支援するのか』と尋ね、バート・ランカスターの老貴族が『生き残るために変わらねば』と答えた」――。
さて、この両者の説明にはある食い違いがあるのだけど、お気づきだろうか? 小沢サンは件のセリフを「あなたのような方がなぜ革命軍を支援するのですか」とたずねた「ある人」に対する答としているのに対して、山田氏は「イタリア統一革命に身を投じた青年」、すなわち甥であるタンクレディに対する答としている点。だからこそ「主客が逆」という指摘にもつながるわけだけれど、この点に限って言えば山田氏が小沢氏の説明を取り違えた? しかし、実は、それも無理からぬと思わせるある事実が存在する。面白いことに、かつては小沢サン自身が著書でそのように説明していたのだ。以下、1996年に刊行された『小沢一郎 語る』(文藝春秋社)の「まえがき」より――
私はいま次の言葉を思い出す。青年時代に見た映画『山猫』のクライマックスの台詞である。イタリア統一革命に身を投じた青年が、自分たちを支援してくれている伯父でもある名門の公爵に「あなたのような方がなぜ革命軍を支援するのか」とたずねた。バート・ランカスターの扮する老貴族は静かに答えた。
「変わらずに生き残るためには、自ら変わらなければならない(We must change to remain the same.)」
そう、1996年当時は小沢サンも件のセリフを「イタリア統一革命に身を投じた青年」――すなわちタンクレディに対するものと述べていたのだ。しかし、その後、第三者から指摘されたか、あるいは、自ら映画を見直すかなどして(「イタリア語・完全復元版」の公開は『小沢一郎 語る』刊行後の2004年)事実関係の誤りに気づいた。そこで、2006年に行った政見演説では「ある人」に対する答と状況説明を変更した――そう推測することも可能。
いずれにしても、小沢氏があえて状況説明を微修正し、件のセリフをタンクレディに対するものではなく、「ある人」に対するものとしている以上、問題の場面は山田コラムが指摘する部分ではなく、他にそれに見合ったシーンがあるのだと考えるのが筋。ただ、これについても産経のコラムでは「字幕を見る限り、イタリア語版でも英語版でも公爵はそんなことは言っていない」と決めつけているわけだけど、確かに「イタリア語・完全復元版」だと185分、「国際版」でも161分に垂んとするこの長尺フィルムのどこにも小沢氏が挙げたようなセリフをドン・ファブリツィオがそのまま口にするというシーンはない。しかし、「似たようなこと」を口にするというシーンなら、ちゃんとあるのだ。それが、この場面――
● 狩り
まだ月影の残る早朝,公爵はドン・チッチョを伴って狩りに出かける.陽も高くなったころ,野うさぎを1匹しとめたところで二人,休む.
公爵「どちらに投票したのかね?」
チッチョ,水をのんでいたが,あわててせきこむ.
公爵「何を恐れている? ここにいるのは私達二人と風と犬だけだよ」
チッチョ「失礼ながら,つまらんご質問ですな.全員賛成なのはご存じのはずだ.ご自身で賛成を勧められたとか」
公爵「その通りだ.では,お前も?」
チッチョ「いいえ! 反対しました.断じて反対しました.ええ,仰せられた事はよく分っています.統合が必要だ,今がその機会だと.多分,その通りでしょう.政治の事はよく分りません.だが,私は信義を重んじる人間です.芸術家失格で,こんなボロを着てはいますが,受けた恩義は忘れません.公爵様もご存じでしょう.あの当時,カラブリア公爵夫人だったイサベラ女王のおかげで勉強ができ,教会のオルガン弾きになれました.勿論,公爵様におすがりした上での話です.だが,貧しいあの頃,母が手紙を書くと,お金がきちんと送られてきました.ですから,天国から王様や女王様がごらんになった時,トゥメオは裏切ったなどと思われたくないのです.私は裏切りません.さいわい天国からは真実が見える」
背後に蝉の声.
公爵「そう興奮するな,……お前の忠誠心は立派だ.しかし,民衆はガリバルディに熱狂している.国民投票をやらねば大混乱がおきる.やむを得ないことなのだ.サヴォイとて王朝だ.お前が敬愛する人々の立場がよくなるとは考えられないが決して滅びはしないよ.全てが以前のままであるためには少々の変化は受け入れねばならぬ.革命の時は終った.このドンナフガータにも生まれた新しいイタリアが栄えればよいが」
ここで話題となっているのは、イタリア統一の是非を問う国民投票。ドン・ファブリツィオは自ら衆人環視の中、賛成票を投ずるというパフォーマンスを披露するなど領内の世論を賛成に導くよう尽力するのだけれど(この限りでは、小沢サンが述べた如く「自己改革の努力」を示したとは言えるはず)、何を思ったか、不意に同行のドン・チッチョ・トゥメオ(領内にある教会のオルガン弾き)に「どちらに投票したか」と訊ねる。虚を突かれたドン・チッチョは、躊躇した揚げ句、反対票を投じたことを告白。そればかりか、一連の政治的変動(特に世人の変わり身の早さに対して?)に激しく怒りを爆発させる。それを精一杯宥めた上でドン・ファブリツィオが口にするセリフが――「全てが以前のままであるためには少々の変化は受け入れねばならぬ」。
どう? これって、小沢サンが政見演説で引用したフレーズと似ていない? つーか、基本的には同じことを言っている。違うのは、「少々の変化は受け入れねばならぬ」――と、いささか「変化」に対して及び腰なことくらい。しかし、「変化」そのものは受け入れている。それは間違いない。そして、なぜ「変化」を受け入れたかといえば、「全てが以前のままであるために」――。それはまさに小沢サンが政見演説で言った通りのことではないか。すなわち――「変わらずに生き残るためには、自ら変わらなければならない」。
実はこの「狩り」の場面(ドン・ファブリツィオとドン・チッチョは狩りの途中、木陰でひと休みしながら↑のような問答を繰り広げる)、ジュゼッペ・トマージ・ディ・ランペドゥーサの原作にほぼ忠実な内容とはなっているのだけれど、ただし一点だけ改変が施されていて、それは怒りを爆発させたドン・チッチョをドン・ファブリツィオが自らの思いを吐露しつつ宥めるという上記のやりとりが挿入されている点。当然、そこにはルキノ・ヴィスコンティならではの意図が込められていると見るべき。加えて言えば、「オリジナル完全版」公開と同じ1981年に刊行された『ヴィスコンティ秀作集3 山猫』(新書館)所収のオリジナルシナリオ(溝口廸夫訳)を読むと「国際版」にも「オリジナル完全版」にも「イタリア語・完全復元版」にもないいくつかの興味深いシーンが用意されていたことがわかる。まずは、物語冒頭、ドン・ファブリツィオが立ち去ろうとるタンクレディを呼び止め「ロトリーノ」を手渡す場面――
タンクレディ「どうしたんですか。革命を援助すると言うのですね。ありがとう、叔父さん」
タンクレディは、おどけた様子で公爵の頬に接吻する。
タンクレディ「じゃ、また、すぐに。叔母さんによろしく」
と急ぎ、階段を駆けおりる。
公爵は階段の途中に立ち止まったまま、遠ざかっていくタンクレディの後ろ姿を見つめている。
公爵「(自問するように低くつぶやく)このままでいたければ、すべてが変わる必要がある?」
もうひとつは、一族を引きつれサリーナ公爵家の領地であるドンナフガータへの長旅の途中、貧しい農家に一夜の宿を求めた場面――
一階の部屋から階段を通じて入ってくる、うす明りに照らされた一室。田舎ふうの二つのベッドに、登場人物の何人かが寝ている。公爵は服をつけたままでベッドのひとつに横たわり、夫人も傍らに寝ている。もうひとつのベッドには、コンチェッタ、カロリーナ、それにカテリーナの三人。寝苦しそうな様子の公爵、何度も寝返りをうち、突然、体をかきむしる。浅い眠りの中で、タンクレディの声に似た声がくり返しくり返し彼をおびやかす。
タンクレディの声「すべてが今あるがままに残るように望むなら、すべてが変る必要があります」
あたかも、タンクレディの声を現実に聞いたかのように公爵は身を起こし、不安そうにあたりを見まわす。眠りこんでいる妻と娘たちを見やる。公爵は、暗がりの中でしばらく身動きもせず耳を澄ます。
こうしたシーンがなぜ本編から省かれたのかは不明なんだけど、制作者の意図を読み解くにはとても貴重な材料。つまり、「魅力的だが、政治的にはやや無節操な」愛すべき青年貴族が口にした多分に戯れ言めいたセリフ――「今のような状態でいたければ全部が変わる必要があるんですよ」に、当初、公爵は拒絶反応を示すものの、心の中にはひとつの〈謎〉として宿ることに。そして、やがてそれは時を経て果汁が自ずと葡萄酒に変化するようにひとつの〈信条〉として発酵するに至る。それが、ドン・チッチョ・トゥメオに向かってためらいがちに放たれた言葉――「少しは何かが変わらなければならなかったんですよ。(ためらって)……全部が元のままであるためには」(件のセリフ、『ヴィスコンティ秀作集3 山猫』所収のオリジナルシナリオだとこうなっている。さすがはオリジナルシナリオに記されたセリフとあって、こうした心境に至るまでの公爵の心の揺れまで掬い取っているかのようで、読ませる。ちなみに、この同じセリフ、「国際版」で表示される字幕だと「多少の変化だけで、すべては元のままだ」。もうニュアンスもヘッタクレもあったもんじゃない。多分、産経や毎日のコラムが声を揃えて「公爵はそんなことは言っていない」――と“小沢批判”を繰り広げることになったのはこの字幕が原因。とはいえ、ちゃんと映画の内容が理解できていれば、わかるはずだと思うんだけどなあ……)。
ということで、「山猫」は確かに小沢一郎サンが「政見演説」で述べたようなことを言っていた。それが物語中盤(小沢サン言うところの「クライマックス」とはちょっと違うかもしれないけれど、ひとつの「山場」であることは間違いない)、いささか苦渋に満ちて吐露された公爵のセリフ――「少しは何かが変わらなければならなかったんですよ。(ためらって)……全部が元のままであるためには」。ただ、これでこの件に関する全ての“疑惑”が解決したかというと……。
映画『山猫』の中盤のハイライト「狩り」の場面でバート・ランカスター演ずる初老の貴族が深い憂愁の中で吐露する政治的「告解」――「少しは何かが変わらなければならなかったんですよ。(ためらって)……全部が元のままであるためには(Something had to change ... for everything to stay as it was.)」。小沢一郎サンが民主党代表選の際の政見演説で“決めセリフ”よろしく掲げた「変わらずに生き残るためには、自ら変わらなければならない(We must change to remain the same.)」がこのセリフを元にしていることは間違いない。ただ、それでは、このセリフを以て、小沢サンが述べた如く、「人類の歴史上、長期にわたって生き残った国は、例外なく自己改革の努力を続けました」とし、小沢流「改革論」への“お墨付き”とすることは、当を得ている?
実は、この点ついてのワタシの見解は、NO。確かに物語において公爵はタンクレディと「新興ブルジョアジーの娘」アンジェリカ(クラウディア・カルディナーレ。絶品)との結婚を後押しし、イタリア統一の国民投票にも賛成する。その限りでは「変革」を身をもって体現したとは言えるのだろう。しかし、同時に、公爵を上院議員として迎えたいという新政府からの誘いに対しては、こう述べてその申し出を謝絶――「わたしは、旧い階級の代表です。わたしは、苦難に満ちた世代、古い時代と新しい時代の間でその両方ともに居心地の悪さを感じている世代の人間です。困ったことに、わたしには幻想が全くないのです」。その上で、次のような厭世的と言ってもいいような人生観を披露して政府から派遣された事務官(シュヴァレー)を困惑させる(以下、『ヴィスコンティ秀作集3 山猫』より)――
公爵「われわれシチリア人は老人なんだ、シュヴァレー。全くの老人なんだ。二十五世紀この方、われわれの肩の上には、すばらしい外国文明がずっしりと重くのしかかってきた。すべてが外からきたものだった。この土地に芽生えたものは、なに一つなかった。二千五百年の間、シチリアは植民地だった。今や疲れ果て、すっかりからっぽになってしまった」
間。時計の音だけが聞こえてくる。
公爵「眠りだよ、シュヴァレーくん。シチリア人が願っているのは眠りだ。そして彼らは、起こしにくるものをますます憎むだろう。実際、よい贈り物を持ってきたとしても。ましてや、今しがた話したように、わたしは新しい王国がシチリアに良い贈り物をするかどうか、全く疑問に思っているのでね」
山田コラムに述べる如く「自らは変化を拒み、誇り高く滅び去る」意思表明。正に「映画の主題は変革ではなく、貴族階級の落日なのである」。そもそも「全てが以前のままであるためには少々の変化は受け入れねばならぬ」とドン・チッチョを諭す公爵ではあるのだけれど、それにつづくセリフは「革命の時は終わった」。そこからは「革命」を一時の熱病のように見なす醒めた姿勢も感じとれるような。さらに言えば、物語序盤、サリーナ邸でのタンクレディとの会話につづく場面では、公爵家お抱えのピローネ神父に対し、「今日は政治的に重大な発見をした」として次のように語っている――
公爵「(……)けさがた、非常に重要な政治的な発見をしたんですよ。今までわからなかったことがやっとわかった。落ち着きをとりもどしました。イタリアは妥協の国です。すべてはあるがままにあるのです。これは、社会階級の交代が考えもなく行われているだけです。ブルジョアたちは、われわれ貴族や神父たちを撲滅しようとしているわけではないのです。ただ、われわれにとって代わりたいだけなのだ。われわれのポケットに上品にやさしく大金を押し込む代わりにね。わかりますか。こうして、すべては今あるがままに続くのですよ」
イタリアは妥協の国です。すべては今あるがままに続くのですよ――。タンクレディが提示した「変革」と「現状維持」にまつわる目も眩むようなパラドックスは、その両者を橋渡しする「妥協」という名の第三項を配置することによって全く似て非なる政治思想(政治的妥協主義)へと様変わりしたようにも見える。とすれば、そのセリフを以て小沢流「改革論」への“お墨付き”とすることは……?
さて、ここで、満を持して(?)、ルキノ・ヴィスコンティその人にご登場願うことにしよう。『ヴィスコンティ秀作集3 山猫』収録の「ルキノ・ヴィスコンティ『山猫』を語る」によれば――
『山猫』の最も重要なテーマ「もしすべてが、今あるがままに残るよう望むならば、すべてが変わる必要がある」に関して言えば、ついに今日にいたるまでイタリアに鉛のコートのように重くのしかかり、真の変化を妨げた政治的妥協主義への冷厳な批判であると同時に、もっと普遍的な現象、残念ながら、今われわれをとり巻いているあいまいで偽善的な方法でもって、古いものを新しいものに置き換えようとする現象への批判でもあるわけです。
このインタビューでは、ヴィスコンティは他にも重要なことを語っている。それは、『山猫』が舞台装置としている19世紀イタリアの国家的大変動――それを「リソルジメント」と呼ぶのだけれど――について、「結論から言えば、わたしもまた、イタリアのリソルジメント(統一)を『満たされなかった革命』、いやそれよりも『裏切られた革命』と定義するものの一人なのです」と述べていること。そう、『山猫』とは、制作者の意図に従うならば、「裏切られた革命」についての映画。作中、公爵の口を借りて語られる「イタリアは妥協の国です」云々というセリフは、イタリア現代史を生きたひとりの知識人が自らの人生を代償として購った痛切なアイロニー――。
以上のような事実を踏まえて、改めてこの物語をふり返るなら――物語序盤、タンクレディは軽快な逆説に満ちた政治的スローガンを掲げた。一方、ドン・ファブリツィオはそこに政治的現実(アイロニー)を見出した。実際、ドラマは、タンクレディの標榜する政治的スローガンのようには進行せず、むしろドン・ファブリツィオが見出した政治的現実のままに進行する。そして、物語のクライマックス(本当のクライマックス)を飾る延々45分にも及ぶ大舞踏会からの帰途、夜空に木霊する数発の銃声(ガリバルディの呼びかけに応じて政府軍を脱走し、アスプロモンテに集結した兵士たちが銃殺刑に処せられる模様)とは、ひとつの「改革」の流産を告げる断末魔の叫び。ここに、映画『山猫』は、ヴィスコンティの言葉を借りるならば、「古い秩序の崩壊(すべては変わらなければならない)と、アスプロモンテのドラマの悲劇的で皮肉な反響(なぜなら、すべては元通りだから)という対立する命題」を見るものに突きつけ、静かに幕を閉じる――。
最後に、私も小沢サンに倣って、この一篇の歴史絵巻から最も印象に残ったセリフを引いてこの小文(え、小文の割には長い? 何分、ダラダラと自説を述べたがる性分なもので)の“決めセリフ”とするなら――公爵の説得を諦め、ドンナフガータを後にする事務官を見送りながらドン・ファブリツィオはふと(自らに言い聞かせるかのように)呟く――「かつてわれわれは、山猫であり、獅子であった。だが、次第に、山犬や羊にとって代わられるでしょう。そして、それぞれが、山猫も獅子も、それに山犬や羊たちも、自らを地の塩と信じ続けながら生き続けるでしょう(We were the leopards, the lions. Those who will take our place will be jackals, hyenas. And all of us — leopards, lions, jackals and sheep — we'll go on thinking ourselves the salt of the earth.)」。今、「山犬」の時代……。
About Me
On PW_PLUS
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②
- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜
- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜
- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜
