久須見健三はなぜヘレン・メリルを聴くのか?
〜ナマシマ・ジローと「日本ハードボイルド」の原風景〜
たまたま島内透の『悪との契約』が手に入ったことがトリガーとなって、島内透→中田耕治→城戸禮と書いてきたわけだけれど、いやー、マニアックだわ。こりゃあアクセスが伸びないはずだ……。
しかもだ、これ以外にもう1本、計画していたものがあって、幸か不幸かテキストの入手に失敗したので断念とは相成ったのだけれど、この人選も相当にマニアックだった。なにしろ、相手は作家ですらない。脚本家なのだから。その名を高岩肇というのだけれど……ご存知の方はいらっしゃいますかねえ。「コルトのジョーさ。命は貰うぜ、親分!〜城戸禮と「国産ハードボイルドの嚆矢」をめぐる一考察〜」で言及した一群の東映「B級アクション映画」の内、『拳銃地獄』(1951年)『暁の市街戦』(1953年)『暗黒街の脱走』(1954年)『二挺拳銃の竜』(1954年)の脚本はこの人。さらには日活製作の『俺の拳銃は素早い』(1954年)という、え、ミッキー・スピレイン? というようなタイトルの映画の脚本も(実はワタシが入手に失敗したというのは、この『俺の拳銃は素早い』の台本。「日本の古本屋」に商品登録されていたんだよね。しかし、勇んで注文を出したところ、「たいへん申し訳ありませんが、現在ご注文の「映画台本俺の拳銃は素早い」は在庫切れとなります」……)。この『俺の拳銃は素早い』について西脇英夫は『アウトローの挽歌:黄昏にB級映画を見ていた』において「多羅尾伴内シリーズの影響が強い」としている。しかし、日活の公式サイトでは「麻薬密輸団を背景に、火を吐く拳銃片手に私立探偵・志津野一平が縦横無尽に暴れまくる活劇娯楽篇」と紹介。この一文からイメージできるのは、多羅尾伴内というよりも、むしろマイク・ハマーなんだけどねえ。しかも、映画が製作されたのは日本出版協同から『ミッキー・スピレーン選集』(この第1巻に『俺の拳銃は素早い』が収められていた)が刊行された翌々年。だから、当時のミッキー・スピレイン人気をあてこんだハードボイルド映画である可能性が高いような気がするんだ。その場合、『俺の拳銃は素早い』は明確にハードボイルドを意識して作られた国産映画の第1号である可能性も出てくる。これだけでも高岩肇に注目する理由としては十分なんだけれど、さらに国立国会図書館サーチで検索したところ、シナリオ作家協会発行の月刊『シナリオ』に「探偵映畫について」(1950年11月号)とか「探偵映画のシナリオ」(1958年7月号)とかいった記事を寄稿していることが判明。高岩肇が「探偵映画」に並々ならぬ関心を持っていたことがうかがえる。ということで、この人物についてもわが国ハードボイルドの〝創世〟に関った群像(というのが、一応、この間、やってきたことの隠しテーマであります)の1人としてクローズアップしようと考えた次第なんだけれど、その格好のテキストとなるはずだった『俺の拳銃は素早い』の台本の入手に(すんでのところで?)失敗。まあね、台本が手に入らなくたって、本編を見られれば問題ないわけだけれど、こちらは台本の入手以上に困難。事実上、見る手立てはないと言っていいのでは? ここは、「デジタル庁」なんてものを作ってまで行政のデジタル化を推し進めようとしている菅政権ではありますから、ぜひ「国立映画アーカイヴ」におかれましてはわが国映画産業の貴重な資産のネット配信に取り組んでくださいますように。
ともあれ、こうして1本の記事が幻となり、わが国ハードボイルドの〝創世〟をめぐってヒマ人が愚考を繰り広げる(不人気)シリーズはこれにて打ち止め――と思いきや、さにあらず。ワタシの中の「酔狂の虫」がもう1本だけ書いてみれば? と(笑)。うん、確かにねえ。あの件ならば書くのは可能だろうし、また書いておくのもまんざら意味のないことではないかなと……。
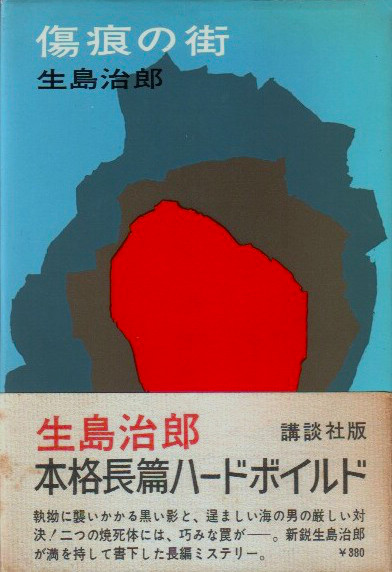
1964年、わが国ハードボイルドの創世のステージに〝大トリ〟よろしく登場してきた生島治郎。何を隠そう、ワタシが最初に読んだハードボイルドはこの人の作品で(確か『薄倖の街』じゃなかったかなあ。この人のビブリオグラフィの中でも相当にマイナーな作品ではないかと思うのだけれど、たまたま近所の本屋にあったのがこの本だった――という記憶がウッスラと残っている……)、それは中学生の頃だった。しかし、すごい中学生だよねえ。普通だったら武者小路実篤の『友情』とか有島武郎の『生れ出づる悩み』とか読んでいるようなトシにナマシマ・ジロー(生島治郎の業界内での通り名。生意気だったのでそう呼ばれていたと、本人がどこかで書いていた)を読んでたってんだから。そりゃあ、ちゃんとしたオトナには育たないわけだ……。もっとも、中学生の頃から読んでいたという割には読んでいる作品はさほど多いとは言えない。多分、生島治郎の全著作(ウィキペディアのビブリオグラフィを元にカウントしたところ119冊)の1割にも満たないのでは? そうだなあ、ここらでじっくりと腰を据えて〝生島治郎三昧〟というのも悪くはないかも。どうせヒマを持て余していることでもあるし……。で、生島治郎といえば自他共に認めるチャンドラリアンとして世に通っているわけだけれど、実際、「作家・生島治郎」の所信表明演説(ホントにそんな内容ですよ。実に初々しい……)といった趣もある『傷痕の街』の「あとがき」ではいきなりレイモンド・チャンドラーの遺作『プレイバック』の一節(例の「タフじゃなくては生きていけない。やさしくなくては、生きている資格はない」という台詞が出てくる下り)を紹介することから始まって、さらには本書の主人公である久須見健三の造形をめぐって「私は自分のマーロウを創りあげるつもりになったらしい」。ところが、そんなことを書いておきながら、同作にはいささかチャンドラリアンらしからぬ描写があるのだ。それが↓。久須見健三が自宅でしばしの休息を取っている場面なんだけれど――
目の前には、染みのついた白い壁があり、その奥の方は本棚でふさがれている。本棚の一番上には、ハードカヴァーのアメリカの本が裏がえしによりかかっていた。そこには、眼鏡をかけ、弱々しい笑みを浮かべた、アル中の探偵作家の写真が刷りこんである。
自分の作品を、自分の思うようにしか書けなかった男で、彼の小説の主人公は、傷だらけの心を、ハードボイルドの仮面で鎧った私立探偵だった。
この作家が、幸福だったのか、不幸だったのか、それは私にもわからない。彼が幸福な生涯を送ったように感じられる時もあり、とてつもなく不幸な男だったと思われる時もある。今も、そのことにこだわりながら、私はグラスをあげて、彼に敬意を表した。
部屋の中は、いつものように、適度な乱れと適度な静けさを保っている。隅にある、小型のステレオには、三日前に聞いたヘレン・メリルのレコードがそのままになっていた。モダン・ジャズにうつつをぬかす年齢でもなく、私にわかるのは、せいぜいヴォーカルぐらいだったが、今はそれを聞いてみようという気分にもなれなかった。
前半部分は、これぞチャンドラリアンの面目躍如、といったところではあるのだけれど、しかし後半部分は? 久須見健三(「あとがき」に従うならば、生島治郎にとっての「自分のマーロウ」)がプライベートで聴いているのが女性ジャズ・シンガーのヘレン・メリルだというのは、いささかワタシの思い浮かべる「チャンドラリアン」のイメージからは乖離しているような……?
なぜヘレン・メリルを聴いていたらチャンドラリアンらしくないのか? それは、レイモンド・チャンドラーが――あるいは、フィリップ・マーロウが、と言い換えた方がいいか?――決してジャズに耳を傾けような人物ではないから。これは、読めばわかる。たとえば、それこそチャンドラーが「自分の思うように」書いたとしか思えない大作『長いお別れ』では――
しばらくしてから、私は映画を見に行った。何を見たのか、ほとんど覚えていなかった。騒音と大きな顔だけだった。家へ帰ると、ルイ・ロペスのものういメロディのレコードをかけたが、やはりなんの感興もおぼえなかった。私はベッドに横になった。
しかし、眠るためではなかった。午前三時、部屋を歩きまわりながら、ハチャテュリアンを聞いていた。彼はそれをヴァイオリン協奏曲と呼んでいた。私にいわせればベルトのゆるんだ送風機だが、そんなことはどうでもよかった。
この短いインターミッションのような場面(『傷痕の街』の↑の下りも、チャンドラーが時おり披露するこういう余談めいた部分を真似たものかもしれないね)でフィリップ・マーロウが聴いているのはハチャテュリアン(ハチャトゥリアン)の「ヴァイオリン協奏曲」。さらに作中にはパウル・ヒンデミットやアルトゥーロ・トスカニーニの名前が取り沙汰される場面もある。そう、フィリップ・マーロウは生粋のクラシック愛好家なのだ。なお、↑の引用部分には「ルイ・ロペスのものいうメロディのレコードをかけた」という下りがあるものの、これは誤訳。原文には「レコードをかけた」などとは記されておらず、「とても退屈なルイ・ロペスを始めた(I set out a very dull Ruy Lopez)」と記されているだけ。で、「ルイ・ロペス」とは何かと言うと、これが「チェスのオープニングの1つ」(ウィキペディア)なんだそうで。さらに「オープニング」とは何かと言うと「ゲーム序盤の駒の動き、つまり定跡及びその変化形の事であり、一般的には第一手から10~15手までくらいの流れを意味している」。もっとも、それを「始めた(set out)」というのがいまいちよくわかんないんだけど。ま、詰め将棋みたいなものなのかな? ともあれ、この場面でフィリップ・マーロウは「ルイ・ロペスのものういメロディのレコード」なんか聴いていない。彼が聴くのはあくまでもアラム・ハチャトゥリアンの「ヴァイオリン協奏曲」――。『長いお別れ』が書かれた当時(1953年)、アメリカ東海岸ではビバップと呼ばれる即興演奏を重視するより自由なジャズが一大ムーブメントを巻き起こしていた。一方、フィリップ・マーロウのお膝元であるロサンゼルスではそれと一線を画したウエストコースト・ジャズと呼ばれるクールなジャズが主に白人ジャズメンによって演奏されていた。しかし、そうしたものにフィリップ・マーロウが関心を示していたことをうかがわせる描写は『長いお別れ』には認められない。生粋のクラシック愛好家である以上、それも当然だろう。ところが、自他共に認めるチャンドラリアンが「自分のマーロウ」を創りあげるべく取り組んだ処女小説において主人公がヘレン・メリルを聴いているというね。なぜ生島治郎は「自分のマーロウ」である久須見健三にクラシックではなく、ジャズを聴かせたのか? というのは、ワタシなどにはなかなか興味をそそられるモンダイ。まあ、こんなことにこれまで関心を示した人間なんて1人もいないだろう。しかし、にもかかわらず、というか、だからこそ、というべきか。なにしろ、島内透→中田耕治→城戸禮(→高岩肇)だから(笑)。これはもう性分というものでして……。
ただ、このモンダイに答を出すのは意外と簡単かもしれない。考えられる可能性はただ1つなので。それは、当時、日本が空前のジャズ・ブームのただ中にあったからだろう。これについては、たとえば、手元の『宝石』1961年2月号を開くと、巻頭の「現代の素顔」と題するグラビアで満員のジャズ喫茶の写真とファンやマスコミに取り巻かれる小林旭の写真を並べて「全く驚くね。現代は正にブームによって動かされているといっても過言ではない」(ちなみに、同誌には河野典生の「くたばれ!アート・ブレイキー」というなんとも風変わりな短編も掲載されている。〝ビート小説〟で鳴らした河野典生にしてからが「くたばれ!アート・ブレイキー」と口走ってしまうくらいには当時のジャズ・ブームは凄まじかったということだね)。そんな時代の空気が久須見健三をして「今さらモダン・ジャズにうつつをぬかす年齢ではないが」と言いつつ、「ニューヨークのため息」と謳われたヘレン・メリルに興味を向かわせたのだろう。
実は、当時のジャズ・ブームの影響は同じ時代に書かれた他のハードボイルド小説にも認められる。たとえば、生島治郎とも少なからぬ因縁がある中田耕治の1961年の作品『危険な女』では、主人公の川崎隆が江波和子という女(いわゆる〝ファム・ファタール〟)と奇妙な関係を持つことになるのだけれど、川崎の目に映った女の部屋の様子はというと――
大きなステレオ・セット、ヒーターがあって、テレビ・セットの上にピカソの陶皿が置いてある。それが、使いなれた感じの、低いベッド兼用の長椅子や腰の低い椅子と不思議なほど調和していた。さして広くない室内や壁の利用できる場所には、モダン・ジャズのレコード・ジャケットがずらりと並べてあった。ソニイ・ロリンズ、J・J・ジャンスンなどにまざって、チャーリイ・パーカーあたりのコレクターズ・アイテムがある。たしかにモダン・ジャズを聞くぐらいの趣味はありそうな女だった。
その後も物語にはキャバレーでジャズを歌っているという女も登場(こちらとも川崎は「奇妙な関係」を持つ。むしろ、奇妙といえばこちらとの関係の方が奇妙かもしれない。なにしろ、最後には、え、もしかしたら結婚しちゃうの? というところまで行くのだから。ところが、シリーズ第2作の『暁のデッドライン』を読んだら……。まるで阿部寛と夏川結衣?)。それに対し川崎隆は「俺はジャズより、五ツ木の子守歌や美空ひばりのほうが好きだな」――と言ったりするのだけれど、多分、それは中田耕治その人の趣味でもあるのだろう。しかし、そういう人物が書いたハードボイルド小説において〝ファム・ファタール〟として位置づけられている女が「モダン・ジャズを聞くぐらいの趣味はありそうな女」として造形され、さらにキャバレーでジャズを歌っているという女まで登場――と、とことんジャズがフィーチャーされているというね。これが当時のジャズ・ブームを反映したものであるのは詮索するまでもないでしょう。
では、当時のジャズ・ブームとはどのようなものだったのか? 実はこれについて語る上で特記する必要のある年が2つある。それは奇しくも『危険な女』が書かれた1961年と『傷痕の街』が書かれた1964年。1961年はアート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズが初来日を果たした年であり、これにより日本には空前の〝ファンキー・ブーム〟が巻き起こることになる(↑で紹介した「くたばれ!アート・ブレイキー」で本当に「くたばれ!」と言っているものの正体)。この初来日時の〝狂騒〟をめぐっては油井正一が『ジャズ昭和史:時代と音楽の文化史』(DU BOOKS)においてこんなふうに回顧しているのだけれど――
一月二日、「東京サンケイ・ホール」の公演は大変な盛況で観客には各界の著名人……お母さん付き添いで暁星の制服着た染五郎、万之助(現幸四郎、吉右衛門)もいたし、岡本太郎もいた。大盛況を喜んだアート・フレンド(招聘元の「アート・フレンド・アソシエイション」のこと――引用者注)は、ロビーで鏡開きをして日本酒の大盤振舞い。
みんなコンサート終了後のパーティー込みで招待状もらっていたと思うんですが、しかしいかに招待とはいえ、これだけの名士が顔を揃えたというのはジャズ・メッセンジャーズが広い注目を集めていたからこそでしょう。
いまの山王飯店の並びにあった「花馬車」という大キャバレーがパーティー会場で、定刻の十時前、僕が着いた時にはコンサートの熱気をそのまま運んでもう異様な雰囲気でしたね。先ほど「サンケイ・ホール」で見かけた各界の著名人が、一階から二階から丸テーブル囲んで早くも主役の登場を待ちかねている。
けれど時間が十時半、四十分と過ぎても一向にブレイキー現れないんだ。初日終えてフラフラでホテル帰って、パーティーには行きたくない、部屋で寝ると言ったらしい。至極当たり前の打ち上げ程度に思っていたに違いないんです。
で、主催のアート・フレンドが部屋まで行って、みんな待っている、とにかく来てくれ。主役いない間に料理はなくなる、酒は追加で予算だってオーバーしちゃっている。とにかくアート・フレンドが必死で連れ出して来て、さあ「アート・ブレイキーさんがお見えになりました!」、アナウンスが流れた途端、あの広いキャバレー狭しと埋めた全員が立ち上がってワーッと拍手したものだから、これにはブレイキーも余程びっくりしたんでしょう。入口に立ちすくんでポカーンと口開けてね、えっ、こんな大変な歓迎だったのか、待たせて悪いことしちゃったなあって顔していました。ブレイキーがふたりの息子に日本名つけるほどの日本びいきになったのは、まさしくあの瞬間であったと僕は思っています。
もっとも、アート・ブレイキーが「ふたりの息子に日本名つけるほどの日本びいき」になったのは、このパーティーとは無関係かも知れない。というのも、招聘元である「アート・フレンド・アソシエイション」の東道輝によれば、この1月2日の公演が終った後、アート・ブレイキーは1人、舞台で泣いていたというので。東道輝が、当時、刊行されていた『ダウン・ビート』日本語版1961年3月号に寄稿した「ジャズ・メッセンジャーズと共に」によれば、公演終了後、続々と引き上げてくるメンバーの中でブレイキーの姿だけが見えない。不思議に思って舞台まで様子を見に行くと「青白い光の下でドラムの前に坐ったままのアート・ブレイキーが泣いているのです。目には大粒の涙をためて」。そして、こう言ったという――「どうか日本のジャズ・ファンの皆様に私のこの気持を伝えてほしい。私は日本に来てはじめて心から歓迎されている自分を見付けました。フランスを初めとして私の行動した国、ヨーロッパ一帯でも、勿論各国で盛大な歓迎を受けましたが、日本ほど心の底から歓迎されたのははじめてで演奏中に舞台の上からハッキリとそれが判りました。私は感謝の気持で一杯です。この皆様の好意にお答えするため日本での演奏を私の生涯に於ける最高のものにしたいと思っています」。もしかしたら、パーティーへの出席を渋ったのも、1人その感激に浸っていたかったからかも知れない……。
ともあれ、こうしたアート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ来日公演の大成功を受けて、以後、毎年のように大物ジャズメンが日本を訪れるようになるのだけれど、特に凄かったのが1964年。1月にエラ・フィッツジェラルド、2月にベニー・グッドマンが2度めの来日、3月にはマックス・ローチ、シェリー・マン、フィリー・ジョー・ジョーンズ、ロイ・ヘインズの「世界4大ドラマー」によるドラム合戦が開催され、さらに5月にはデイヴ・ブルーベック・カルテット、そして7月には当時、ニューポート、モンタレーと並ぶジャズの祭典と喧伝された「第1回世界ジャズ・フェスティヴァル」がこの日本で開催され、遂に〝帝王〟マイルス・デイヴィスが第2期クインテット(ただし、サックスはジョージ・コールマンではなくサム・リヴァース。来日2週間前にジョージ・コールマンに代って参加し、1か月ほどツアーに同行しただけでウェイン・ショーターにバトンを引き継いでいる)を率いて日本初上陸――と、一連の来日ラッシュはここに1つのハイライトを迎えたと言っていい。ここでは、今なお語り草となっているマイルス・デイヴィス・クインテットの公演の様子について、アメリカのレナード・フェザーという評論家が書いた文章の一節を小川隆夫著『伝説のライブ・イン・ジャパン:記憶と記録でひもとくジャズ史』(シンコーミュージック・エンタテイメント)より紹介するなら――
アメリカから同行した評論家のレナード・フェザーは、次のように報告している。
「小柄なイタリアン・スーツを着た端正なアメリカ人が、シャンソンの〈枯葉〉が持つ翳りある最初のテーマ・メロディを吹き出すやいなや、嵐のような拍手が沸き起こった。あの興奮は、フェスティヴァル全体を通して、他に比較できるものがなかった。マイルスのコンサートは、5000席(実際は約3000席)ある日比谷野外音楽堂を満員にし、次いで厚生年金会館大ホールでも行なわれた。
しかし、ツアーの中でももっとも印象的だったコンサートは、京都の円山公園音楽堂でのものだ。マイルスのセットの間に小雨が降り始めた。雨は次第に強くなっていったが、80人程度の若いファンがステージ脇の屋根がある場所に移った以外、数千人の聴衆は雨に打たれるまま、席を立とうとしなかった。傘をもっていたのは数百人くらいのものである。
マイルスのセットが終わり、彼が花束を受け取ったのち、カーメン・マクレエがステージに登場し、〈ヒアズ・ザット・レイニー・デイ〉を歌い始めた。そのとたん、雨はピタリとやんだのだ!」
最後の感嘆符にこの日の彼の感動が凝縮されていると言えるのかな? ともあれ、当時、既に「帝王」(あるいは「神」。上掲書にはこのフェスティヴァルの主催者である「ジャパン・ブッキング・コーポレーション」のスタッフだったという人物がマイルスに挨拶した際に言われたという「オレは神様のようにオールマイティだ(I'm almighty as GOD)」という言葉も紹介されている)と畏れられていたマイルス・デイヴィスまでが参加する大規模なジャズ・フェスティヴァルが開催されるほどには当時の日本におけるジャズ人気は絶大なものがあった。だからこそ中田耕治は『危険な女』において〝ファム・ファタール〟という重要な役柄に「モダン・ジャズを聞くぐらいの趣味はありそうな女」をキャスト。そして、自他共に認めるチャンドラリアンである生島治郎までもが「自分のマーロウ」である久須見健三にヘレン・メリルを聴かせることになったわけだね。これは、少しばかり見方を変えるならば、わが国におけるハードボイルドの〝創世〟が空前のジャズ・ブームのただ中で起きたということであり、かの有名なセロニアス・モンクのテーゼ(?)にことよせて言うならば「ジャズとハードボイルドは手をつないでゆく」――という状況が現出した、ということにもなる。そして、ここでどうしても強調しておかなければならないのは、こうした状況は日本特有だったということ。本国アメリカは、こうした日本の状況からはほど遠かった。既に記したように、「ハードボイルド私立探偵」のシノニムと言ってもいいフィリップ・マーロウはクラシック音楽の愛好家であり、ビバップはおろかウエスト・コースト・ジャズにすら興味を示さない。またレイモンド・チャンドラーの後継者と目されるロス・マクドナルドはリュウ・アーチャー・シリーズの第1作である『動く標的』にベティというジャズ・シンガー(なんだろうなあ。歌っているのは「派手なブギウギのジャングル」だったり「退廃的な」ブルースだったり)を登場させるのだけれど、彼女との会話を記す中で「ホット・ジャズはわたしは好きではなかった」。これまたリアル・ジャズは趣味ではないようなのだ(ただし、リュウ・アーチャーはファッツ・ウォーラー、レッド・ニコルズ、ミード・ラックス・ルイス、メアリー・ルー・ウィリアムスという名前は「聞いたことがある」らしい。そういう記述も後半には出てくる)。
こうしたアメリカン・ハードボイルドとジャズの〝疎遠な関係〟は別の事実からも裏付けることができる。それは、ハードボイルド映画の音楽担当者。レイモンド・チャンドラーの『大いなる眠り』を映画化したハワード・ホークス監督の『三つ数えろ』(1946年)はマックス・スタイナー。ジャック・スマイト監督の『動く標的』(1966年)はジョニー・マンデル。ポール・ボガート監督の『かわいい女』(1969年)はピーター・マッツ。ロバート・アルトマン監督の『ロング・グッドバイ』(1973年)はジョン・ウィリアムズ。ディック・リチャーズ監督の『さらば愛しき女よ』(1975年)はデヴィッド・シャイア。いずれも白人の(ちゃんとした音楽学校を卒業した)音楽家が担当。一方、たとえばフランスではルイ・マル監督が『死刑台のエレベーター』(1958年)の音楽にマイルス・デイヴィスを起用。またロジェ・ヴァディム監督も『危険な関係』(1959年)の音楽にセロニアス・モンクを起用した(演奏にはアート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズも参加している。「危険な関係のブルース」は日本でも大ヒットした)。さらに日本でも河野典生の「腐ったオリーブ」を映画化した蔵原惟繕監督の『黒い太陽』(1964年)にはマックス・ローチ・カルテットとアビー・リンカーンが演奏と歌で参加――。海外ではジャズ・ミュージシャンが盛んに映画音楽に起用される一方、本国アメリカでは白人の(ちゃんとした音楽学校を卒業した)音楽家が一貫してハードボイルド映画の音楽を担当しつづけている……。
これはいささか鼻白むというか。「ハードボイルド」を取り巻く状況が、本国アメリカとフランスや日本ではあまりに違う。有り体に言うならば、アメリカン・ハードボイルドは「白い」。これは、否定しようのない事実。基本、アメリカにおいては、「ハードボイルド」とは白人のものなのだ。だからこそチェスター・ハイムズは母国を捨ててフランスへ渡らざるをえなかった。そして、彼の地で不動の名声を獲得することに成功した……。いずれにしても、ことアメリカにおいては、とてもじゃないけれど「ジャズとハードボイルドは手をつないでゆく」というような状況ではなかった。それはすぐれて日本的な現象であり、あえて言うならば、1961年の初来日時にアート・ブレイキーが「私は日本に来てはじめて心から歓迎されている自分を見付けました」と言って感激の涙を流したような国だからこそ起こりえた出来事だったのだ。そういうことを書いておくのもまんざら意味のないことではないかなと……。
ジャズと自由は手をつないでゆく
わが国におけるハードボイルドの〝創世〟が空前のジャズ・ブームのただ中で起きたということであり、かの有名なセロニアス・モンクのテーゼ(?)にことよせて言うならば「ジャズとハードボイルドは手をつないでゆく」――という状況が現出した。
本文でワタシはこう記したわけだけれど、もしかしたらその「セロニアス・モンクのテーゼ」なるものを誰よりも熱く受け止めたのはわが日本の文士たちだったかもしれない。ワタシが知っている限りでも、3人の著名な作家が著作で引用したり活用したりエピグラフとして掲げたり。たとえば、寺山修司は1966年に発表した唯一の小説『あゝ、荒野』の第13章で――
実際、新宿は夜明けの時刻が一番美しい。朝靄の晴れかかってゆくコンクリートの上にはだしで出て来ると、遠くから疲れきった深夜喫茶のモダン・ジャズが路上へ流れだして来る。ひろい、誰も通らない表通りのキャバレーのごみ箱を老犬が漁っている。日が昇りきると入れかわりに街灯が消える。この街灯の消えてゆくのを目でたしかめられる爽やかさはたとえようもなくいい。晴れた路上から朝靄ののこっている闇に向ってロード・ワークの少年たちが駈け去ってゆく。あくびをしながら、連れこみホテルを出て来た街娼が、吸いさしの煙草を映画のポスターの二枚目俳優の顔でこすり消す。路上でパークしているタクシーの中では、夕刊のスポーツ紙を顔にのせた運転手たちがハンドルにもたれたり、シートにうずくまったりして眠っている。日中稽古のできないバンド・ボーイの吹くトランペットの音が伊勢丹裏の密閉したガレージのシャッターから洩れて暁の街に流れ出す。その音には、朝の冷気に向って胸をひき裂くようなひびきがある。都電の車庫から区役所通りへ折れると、酔っぱらいが電柱にもたれて立ったまま眠っている。その手には、アパートで待っている一人息子のために買った土産のミニカーの包みがぶら下がっている。誰もいないということは壮烈である。それは「朝は死んでいる」のではなくて「朝はこらえている」からなのだ。パンツ一枚の男が手に背広やズボンを横抱きにして路上を横切ってゆくのは、コキュの逃走と言う感じよりも、自由という感じがする。自由と言えば、モダン・ジャズ喫茶が夜の最後にかけるレコードは、きまってセロニアス・モンクだ。
Jazz and freedom go hand in hand(ジャズと自由は手をつないでゆく)そこから、手をつなぎそこねて出てきた胃弱の大学生が、朝の偉さにうたれて思わず前のめりに電柱にもたれて嘔吐する。こみあげてくるものは、怒りと言うにはあまりにも非力なその豆〔ママ〕や支那竹や、回虫のようにとぐろをまいた中華麺だ。だが、彼は出すべきものを出してしまうと再戦をいどみに、ジャズ喫茶にとびこんでゆく。そしてまた、麻薬中毒のピアニストが悪夢のなかに想いつづけた「自由」をリクエストするのだ。(略)
いかにも寺山修司的なイメージのてんこ盛り。「吸いさしの煙草」だの「立ったまま眠っている」だのはそれこそどこかで聞いたようなフレーズ。そして、そんな寺山修司的世界観がとっくりと披露された記述の中に「セロニアス・モンクのテーゼ」はなんと違和感なく納まっていることか。ワタシはかねがね寺山修司を引用の達人と思っているのだけれど、↑の下りなどはそれを再確認させてくれるものと言っていい。なお、寺山修司は1973年が初刊となる『ポケットに名言を』でもこの「セロニアス・モンクのテーゼ」を紹介している。よほどお気に入りだったんだろうねえ。
また、1967年には五木寛之が『青年は荒野をめざす』の中でこの「セロニアス・モンクのテーゼ」をいささか改変した上で使っている。主人公であるジュン(北淳一郎)が世界放浪の途中、パリで出会ったレッド・シルバーというピアニストとの会話の中で――
「どこから来た?」
と、レッドがきいた。彼はうさん臭そうな目付きでジュンを見おろした。
「東京から来ました」
「トウキョウか――」
レッドは大きなため息をついて首をふった。
「三年前に行ったよ。あれは面白い街だった。えーと、なんと言ったかなあ。シンジュキ、いや、サンジュク――」
「シンジュクでしょう」
「それだ、シンジュクの〈ペイパー・ムーン〉という店に遊びに行ったっけ。女の子にえらく持てたんだ。このおれがだぜ」
「ぼくは〈ペイパー・ムーン〉で吹いていたんです」
「君が? それじゃあ、あの店の壁におれが残してきた落書きを覚えているね。トイレットの壁にさ」
ジュンは微笑してうなずいた。
「覚えていますとも。あれは――」
レッドが首をかしげてジュンの顔をのぞきこんだ。ジュンはその文句を思い出して言った。
「ジャズと自由は、手をつないでやってくる――そうですね」
セロニアス・モンクのオリジナルでは「ジャズと自由は手をつないでゆく」――と主体的な表現になっているのに対して、五木版では「ジャズと自由は、手をつないでやってくる」――と客体的な表現に変わっている。この改変が意図されたものなのかどうかは何とも言えないのだけれど、仮にジャズの生産国=アメリカと消費国=日本の関係性を反映させた――とするならば、なかなか奥が深い、とは言えるかな。
さらに、1975年には河野典生が『明日こそ鳥は羽ばたく』の巻頭にこの「セロニアス・モンクのテーゼ」をエピグラフとして掲げた。こちらでは『青年は荒野をめざす』のような改変が施されているわけではないのだけれど、寺山版とは訳が違っていて――
ジャズと自由は手をたずさえて行く
――と、こうしてワタシの言う「セロニアス・モンクのテーゼ」はわが日本の文士たちによってくり返しメンションされてきたわけで、これもまたいかにも日本的な現象だとは言えるのかなあ、と。それはやはりアート・ブレイキーが「私は日本に来てはじめて心から歓迎されている自分を見付けました」と言って感激の涙を流した、この国ならではの出来事であるのは間違いないのでは?
もっとも、今、この「セロニアス・モンクのテーゼ」が、どの程度、人々に知られ、支持されているかとなると、かなり微妙では? あるいは、『エスクァイア』1959年1月号(The Golden Age of Jazzと題したジャズの歴史においても画期的と評される特集の中。現在はウェブ版が公開されている)の誌面を飾ってから早くも60年が経過。かつてのようにこの「セロニアス・モンクのテーゼ」を熱く受け止める空気はもはやこの国には存在しない? そもそもだ、今や「自由」という言葉の意味が全く違うものになってしまったと言ってもいいくらいなのだから。むしろ言いづらい――というか、言いたくないよね、「ジャズと自由は手をつないでゆく」なんて(なにげに竹○平○はプライベートではジャズを聴いているのではないかという気がして、イマイマシイ)。あゝ、ワレワレは今、何という時代を生きているのだ……。
About Me
On PW_PLUS
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②
- ◦そのぷろふいる、偏見につき〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜
- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜
- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜
