ペーパーバックの倉庫から④
2011.11.16
ダシール・ハメットのThe Thin Manの日本初訳は1950年、雄鶏社の「おんどり・みすてりい」の1冊として刊行された『影なき男』(砧一郎訳)――と11月10日付けエントリでは書いたんだけど、どうもこれが違うらしい。実は小鷹信光著『私のハードボイルド 固茹で玉子の戦後史』の「研究編」レポート3「日本ハードボイルド輸入史――戦前編」にこんなことが記されているのを発見――
……映画化で評判になった『影なき男』(日本公開は一九三五年)の抄訳(大門一男)が一九三四年一月に映画雑誌《スタア》に分載された。未見なので確かなことは言えないが、これも原作からの抄訳ではなく〝映画ストーリー〟のようなものだったのではないだろうか。
へえ、と思って調べてみたところ、確かに『スタア』1934年1月上・下旬号に「影のない男」として連載されている由(ソースは江戸川乱歩の「探偵小説雑誌目録」。またMISDASにも記載あり)。まあ、戦前のことなので、当然、「無断翻訳」だったのだろうけれど……しかし、これは相当にケッタイな話ですよ。だって、掲載紙は1934年1月刊行なんでしょう? 小鷹レポートではこの翻訳について「原作からの抄訳ではなく〝映画ストーリー〟のようなものだったのではないだろうか」としているのだけれど、映画『影なき男』の日本公開は1935年7月。またアメリカでの公開は1934年5月。仮に『スタア』掲載の「影のない男」が「〝映画ストーリー〟のようなもの」(一種のノベライゼーション?)だとしたら、当然、書いた人間はその映画を観ていなければならないのだけれど、ちょっと時系列が合わんのだ。
となると原作からの抄訳である可能性が高くなるのだけれど、その場合、テキストは? The Thin ManがAlfred A. Knopfから刊行されたのは1934年1月。大門一男訳「影のない男」が掲載された『スタア』1月上・下旬号の発売と同年同月。また現在でも雑誌の刊行は実際のカレンダーよりも1か月前倒し。おそらく上旬号などは前年の12月には発売されていたのでは? とすると大門一男がAlfred A. Knopf版をテキストとした可能性はまず考えられない。そうなると残る可能性は――小説が最初に掲載されたRedbookをテキストとしたケース。Richard LaymanのShadow Man: The Life of Dashiell Hammettによれば、The Thin ManはRedbookの1933年12月号に掲載。で、これも刊行は実際のカレンダーより1か月前倒しだったと仮定すると、発売は11月。それをいち早く大門一男が入手、『スタア』1934年1月号に訳出――、これならばギリギリ間に合う?
いや、待て。昨日、アメリカで発売された雑誌が今日、日本に届く。そんな時代じゃないんだ。何しろ、まだ日米間に定期航空便もなかったんだから(羽田飛行場への定期航空便の乗り入れは1947年、ノースウエスト・オリエント航空のシアトル―東京便が最初)。当然、輸送は船便。とすれば、たっぷり1か月はかかったはず。そう考えると、とても『スタア』1934年1月上・下旬号に間に合うかたちでRedbook1933年12月号を入手し、あまつさえ翻訳するなんてコトは無理だったような。うーん(それにしても、思いもかけない謎に遭遇したもんだ。コレまで誰も疑問に思わなかったんだろーか?)。ちなみに『スタア』1934年1月上・下旬号なんだけど、1984年、南部圭之助監修による全10冊からなる『「スタア」複刻版』が刊行。このセットには1934年1月上旬号も含まれているらしい。ワタシA「ほう。で、お値段は?」ワタシB「何でも定価28,000円とか」ワタシA「……」。
追記(2011.11.21)
定価28,000円に思わず言葉を失った南部圭之助監修『「スタア」複刻版』(国書刊行会)。タテ40cmヨコ29cmの堂々たる外箱(いわゆる筒箱)からオソルオソル中身を引き出すと、現れ出でたる内箱はさらに同じ紙質の厚紙で包むように守られている。その包み紙(?)(多分、和本の世界で「帙」とか「たとう」とか呼ばれているやつ)を開き、内箱の蓋を玉手箱よろしく開くとようやくお目にかかれるのが御本尊(とでも言いたくなるような丁重さ)の『スタア』復刻版(全10冊)。その1冊、1934年「新年特別號」こそワタシのお目当ての品。サイズは、B4よりもさらに一回り大きいくらい(何でも四六四倍判というサイズとか)。その48ページから51ページまでがモンダイの大門一男譯「影のない男」。8段組み、5号くらいの活字でみっしり。字が小さい上に、旧字、旧仮名遣い、加えてこの当時定番の総ルビと、読み難いことこの上ない。
しかし、そんな“昭和モダン”の洗礼に戸惑いながらもどーにか読みすすんで行った結果、断言できること。それは、これが決して「〝映画ストーリー〟のようなもの」ではなく、紛うことなき原作からの直訳であるという事実(ただし、抄訳。いかに大判とはいえ、わずか見開き4ページ。それで、全31章からなる原作の11章までカバーしている。なお、12章以降は1月下旬号に分載)。しかし、これでいよいよわかからなくなった。本国アメリカではRedbookの1933年12月号が初出。そんな小説が、太平洋を隔てた日本で1934年1月には早くも翻訳紹介。しかもこの「新年特別號」、奥付によれば「昭和八年十二月廿五日印刷納本」。当然、入稿はそれ以前。翻訳に要する時間も考慮に入れれば、一体いつ原作を入手すれば「昭和八年十二月廿五日印刷納本」などというスケジュールに間に合うのか。ハッキリ言って、不可能という気がするんだけれど……。
しかし、現にダシエル・ハメット作「影のない男」が目玉記事よろしく誌面を飾る『スタア』1934年「新年特別號」(の復刻版)は今、ワタシの目の前に。『スタア』編集部は何らかの手づるを使って「昭和八年十二月廿五日印刷納本」というスケジュールに間に合うかたちで原作を入手していたと考えるしかない。恐るべし、『スタア』。恐るべし、南部圭之助。何しろ、11月10日付けエントリでも記しているように、「影のない男」の原作であるThe Thin Manはカナダでは出版差し止め、イギリスではアメリカから4か月遅れの発売。ということは――そう、この1934年1月という段階で「ハメットを時代の寵児であるベストセラー作家に仕立て上げた」(ハヤカワ文庫版『影なき男』訳者あとがき)小説を読むことができたのは、アメリカと日本だけ。まだ日米間に定期航空便すらなかった時代に実現した奇跡の「日米同時出版」……。
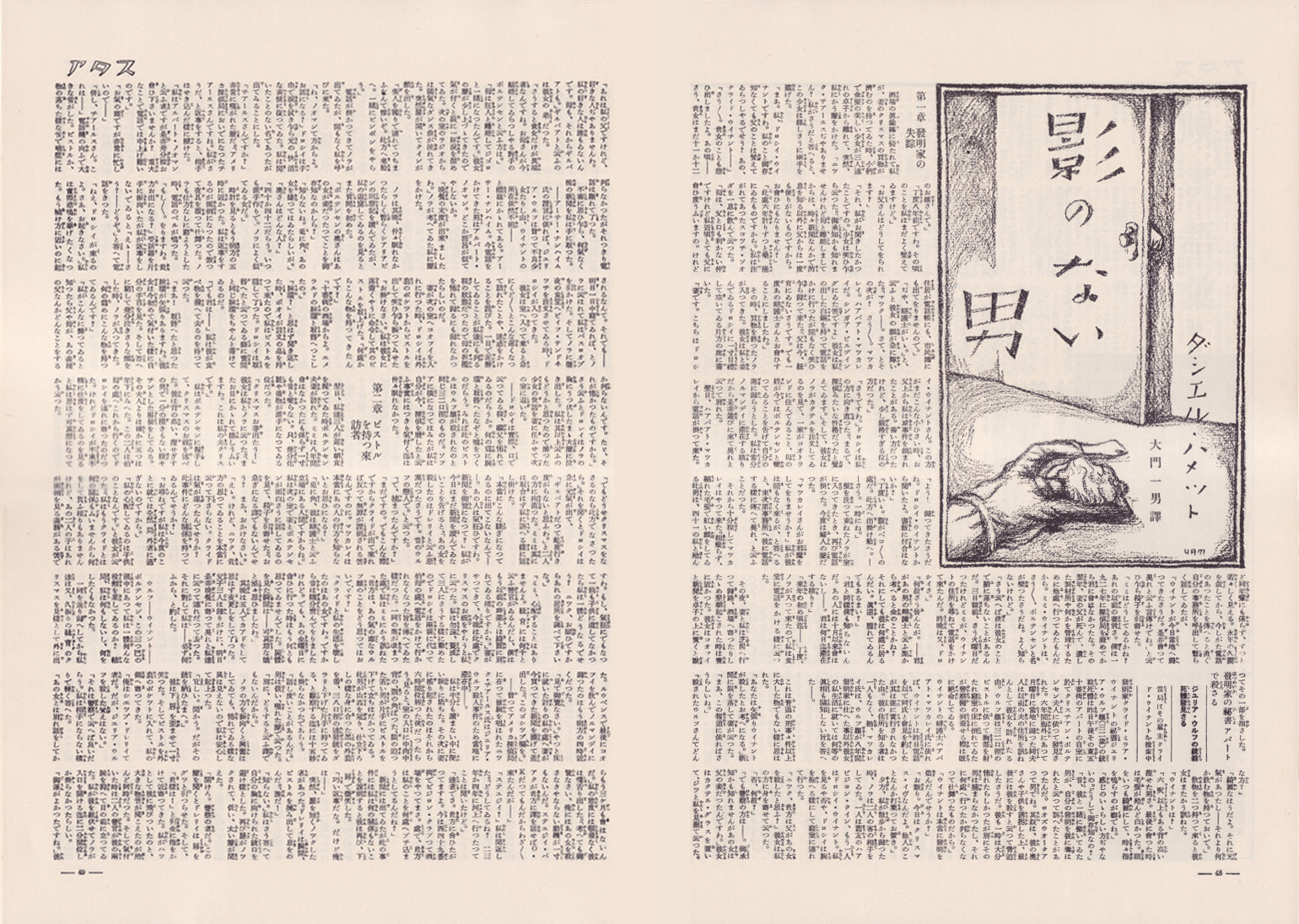
2011.11.25
ダシエル・ハメット作「影のない男」の奇跡の「日米同時出版」を実現した『スタア』1934年1月上旬号には他にも4編の翻訳ミステリやショートストーリーが掲載。このうち、「ロオマ劇場事件」は1933年8月上旬号から1934年5月下旬号にかけての長期連載。「非常に長く續きますが、御愛讀を賜はれば幸甚です」(1933年8月上旬号巻末の「夏を送る」と題する編集後記。署名は「N・K」)。これが「エラリイ・クヰーン」のデビュー作となるThe Roman Hat Mysteryの記念すべき本邦初訳。また「影のない男」は1934年1月下旬号との分載。「讀切が十頁近くになつてしまつたので殘念ながら二分してしまつた。この素睛らしさで御勘辨願つて次號まで解決を待つて頂く。犯人そも誰? 御想像がつきますか」(1934年1月上旬号「編輯雑筆」)。残る3本はこの「新年特別號」のための「讀切」というコトになる。さて、どんな作品?
1本はG・K・チエスタトン作「消え失せた五人の男」。原作は、後にThe Blast of the BookとしてThe Scandal of Father Brownに収録されるThe Five Fugitives(初出はLiberty1933年8月号)。しかし、残る2作、I・A・ウイリアムス作「ペリカンを盗む」とH・マチスン作「雨の日」については、作者の特定すら困難。誌面には、著者名の英語表記もなければ、そもそも作品の原題すら記載されていない。そんな中、何とかGoogleの助力を得て前者についてはIolo A. Williamsなる人物らしいことはつきとめたのだけれど(掲載作品は1933年5月刊行のThe Evening Standard Book of Best Short Storiesに収録のThe Man Who Stole the Pelicanと思われる。ソースはこちら)、後者については特定を断念。つーか、目次には「H・マチスン」とあるのだけれど、掲載ページを開くと「ハロルド・タムスン」。「マチスン」なら、まあ、Mathesonか。「タムスン」なら……Thomson?
と、まあ、やはり「無断翻訳」だと原作に対するリスペクトも失われるのかなあ、と。もちろん、正確を期すならば、「ロオマ劇場事件」や「影のない男」については原産国(?)がアメリカなので日米著作権条約に基づいて天下御免の「翻訳自由」。しかし、「消え失せた五人の男」や「ペリカンを盗む」は原産国はイギリス。であるならば、歴としたベルヌ条約の保護対象。同条約には10年未翻訳で翻訳権消失とする条項(パリ追加改正条約第五条第1項)が設けられていることは、当ブログでも11月1日付けエントリなどでさんざん述べてきたところだけれど、両作品はいずれも初出は1933年。とすれば、当然、許諾契約を結んだ上で翻訳されているはず……なのだけれど、何だか不安だなあ。実は乾信一郎著『「新青年」の頃』(早川書房)にこんな一節があるのだ――
……実はその頃国際的な翻訳権とか著作権とかいったことから日本は除外されていたからなのだ。というのは、情ない話だが、日本は国際的に低文化国とみなされていて、他国のすぐれた文化の取り入れ中というようなわけで、著作権料とか翻訳権料など支払わずに済んでいたのだ。
うーん、当時、実際に『新青年』の編集に携わり、また自らも翻訳を手がけるなどしていた人物の認識がこのようなものだったとすると、『スタア』も推して知るべし……。しかし、この件はこれまで。70年以上も前の“著作権侵害疑惑”をこれ以上詮索してもセンナキコト。むしろ、『スタア』1934年「新年特別號」に掲載されたのが、既に翻訳権切れとなった10年以上も前の旧作などではなく、いずれも新作、しかも、その内の3編は前年に発表されたピカピカの新作であったことは評価されていい。もちろん、読者には旧作か新作かを判断する材料などなかっただろうけれど、それをいいことに旧作でお茶を濁すなんてコトは南部圭之助にはできなかったのだろう。そう考えれば――大門一男譯「影のない男」も掲載されるべくして掲載されたのかなあ、と……。
2011.11.28
それにしても、デカイ。あまりにもデカイのでわが家の本棚には立てて収納することができず、本とヨコ板の隙間に寝かして収納。すると実にハードカバー18冊分にも相当。この現在ではちょっと考えられないようなサイズ、11月16日付けエントリへの追記では四六四倍判と紹介したのだけれど、『「スタア」複刻版』別冊で南部圭之助自身はタブロイド判と表現。なるほど、そう説明した方がわかりやすかったかな。この別冊にはバーバラ・スタンウィックという女優さんが『スタア』を見入っている写真も載っているのだけれど、まさに「スター、タブロイド紙に見入る」の図。何でも南部圭之助によれば当時は「サンデー毎日」「週刊朝日」「アサヒグラフ」などもこのサイズだったのだとか。いや、単にサイズで拮抗していただけではない。これも南部圭之助が書いていることだけれど、「昭和九年から十二年にかけての発行部数は約八万五千。当時『サンデー毎日』は約十三万、『週刊朝日』は十二万」。発行部数でも十分、いい勝負していたのだから、立派。
で、そんな『スタア』なんだけど、1933年6月、松竹をスポンサーに「映畫とレヴユー」の専門雑誌として誕生。それが、なぜ翻訳ミステリを? これについて江戸川乱歩は「探偵小説雑誌目録」(『幻影城』所収)で「同人に西洋探偵小説通が多く、頻々として探偵物の翻訳や紹介をした」云々と記載。歴とした商業誌でありながら「同人」とは、当時の編集者のひとり藤井田鶴子の「あれだけ部数が出ていても、本当に同人誌的な要素がありましたね」(『「スタア」複刻版』別冊)とする証言とも符号。ま、必ずしもスポンサーのグリップが強くなかったというコトかな? ともあれ、創刊号には当時『新青年』の編集長だった水谷準が「探偵映畫問答」を寄稿。また、1933年8月上旬号に「風船玉と猫」と題するちょっと小洒落たショートストーリーを提供している乾信一郎も当時、『新青年』編集部に所属。一方、南部圭之助はというと、その『新青年』で映画欄(シックシネシック)を担当。これだけ人脈がクロスオーバーしていれば、そりゃあミステリ色が強くなるワケだ。
中でも特記すべきは「エラリイ・クヰーン」の紹介か。第1弾となった「ロオマ劇場事件」を皮切りに「支那オレンヂの秘密」「ハートの4」。エラリー・クイーンはこの時代、『探偵小説』『新青年』『ぷろふいる』などのミステリ専門誌が競うように掲載。それらに伍してEQ紹介の一翼を担った『スタア』は、看板こそ「映畫とレヴユー」だけれど、実質的には「映畫とレヴユーと翻譯ミステリ」の雑誌だったということかな。思えば映画やレビューやミステリを誰気兼ねなく楽しめたのもこの頃まで(あれほど盛んだったEQ紹介も「ハートの4」を最後にパッタリ)。ほどなくこの国は暗雲に飲み込まれ、『スタア』も1940年、当局のお達しにより他の4誌と統合、『新映画』といういかにもおざなりな名前の新雑誌に。その「最終號」の「最終頁」(わざわざ「質問室」を挟んで結末部分のみ最終ページに割り込ませている)を飾るのがレツクス・スタウト作「辛い結末」だったのは、一見、希望に満ちた「終刊の辭」からはうかがい知ることのできない南部圭之助その人のココロの辞……。
付記 文字通り『スタア』の掉尾を飾るコトになった「辛い結末」なんだけど、原作はBitter End。初出はThe American Magazine1940年11月号。一方、『スタア』最終号は「昭和十五年十一月二十日印刷」。もうこの際、「南部マジック」とでも呼ぶしかないね。
○
About Me
On PW_PLUS
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②
- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜
- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜
- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜






