テールズ・オブ・ザ・コピーライト・ミュトス
〜オーガスト・ダーレスと「著作権の黒い海」〜
H・P・ラヴクラフト(以降、表記はHPLとします)の読者ならば、当然、ご存知だと思うのだけれど、かつてはHPLの著作権はアーカム・ハウスが持っている、ということになっていた。またこのことはアーカム・ハウスが繰り返しアピールしてきたところでもあって、時には法的手段をチラつかせるなどの方法も駆使してその既成事実化を図ってきた。しかし、このアーカム・ハウスの主張は、ウソだった。その証拠にHPLのほとんど(あくまでも「ほとんど」。決して「すべて」ではない。これはなかなか一筋縄では行かない問題ではあるのだけど、アメリカ著作権法303条によって保護されているものもあると考えられる。対象となるのは「1978年1月1日より前に創作されたが、発行されず又は著作権による保護を受けることのなかった著作物」。また、それ以外でも、別の根拠で著作権の保護対象になっている作品があるのではないかとワタシは考えているのだけど、これについては本稿では触れません。正直、自信が持てません……)の作品は、現在、パブリック・ドメインとなっている(あるいは、そう見なされている)。もしアーカム・ハウスが本当にHPLの著作権を持っていたのならばこんなことにはなっていないはず。今でもHPLの著作はアメリカ著作権法に従ってしっかりと保護されていたはず。しかし、現実はそうはなっておらず、HPLのほとんどの作品は今やパブリック・ドメイン――という事実を踏まえるならば、導き出される答は1つ――アーカム・ハウスはウソをついていた……。
ところが、ここに摩訶不思議な現実がある。アーカム・ハウスがこの件で訴えられたということは、知られている限りでは、ないんだ。これがなんとも理解不能で、ワタシなんかはHPLと著作権をめぐるモロモロの謎(これについてはウィキペディア英語版にわざわざ項目が立てられているくらいで、HPL研究の重要なイシューとなっている)の中でも最大の謎ではないかと思っているくらいなんだけど……もしかしたらこの謎に一定の解を提示しうる――かもしれない、あるストーリーに思い至ったので、以下、少しばかり。
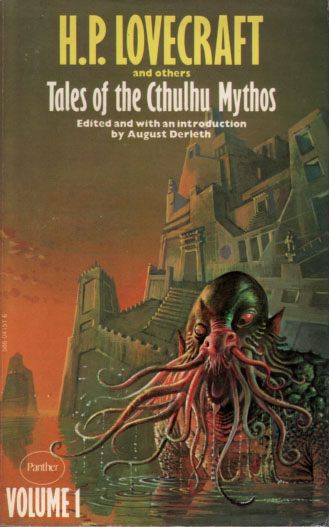
まずは、なぜ現在、HPLのほとんどの作品はパブリック・ドメインであると見なされているのか? という基本的な部分から。これは、煎じ詰めるならば、HPLのほとんどの作品は著作権存続のために必要な更新手続が取られていない(あるいは、取られていることを確認できない)から――ということになる。ここでこの問題を理解するために必要なアメリカ著作権法の仕組みを簡単に説明するなら――かつてアメリカ著作権法では著作権の保護期間は登録から28年と定めた上で、更新手続が取られることを条件にさらなる保護期間が認められるというかたちになっていた。また2度目の保護期間は28年→47年→67年と、法改正の度に延長されて行った。これにより、更新手続が取られるかどうかで、パブリック・ドメインとなるまでの期間が最短で28年、最長で95年という大きな違いが生じることになる。なお、これは1978年1月1日より前に発表された著作物に関してで、1978年1月1日より後に発表された著作物に関しては、著作権の保護期間は一律で著作者の生存期間+死後70年とされていることはご承知の通り。しかし、HPLは当てはまらないので、横に置いてもらって構わない。で、かつてアメリカ著作権法では著作権の保護期間は登録から28年と定めた上で、更新手続が取られることを条件にさらなる保護期間が認められるというかたちになっていた――というところに戻って、HPLのほとんどの作品はこの著作権存続のために必要な更新手続が取られていないのだ。著作権の更新状況についてはスタンフォード大学のCopyright Renewal Databaseで確認することができるのだけど(それにしても、なんか、スゴイね、アメリカって。こんなものまで用意されているのかという。確かにこういうものがあるおかげで、HPLの著作のほとんどは既にパブリック・ドメインである、というようなことを素人でも容易に確認することができる。こういうものが提供される以前は、著作権の更新状況の確認はすべて手作業。それは並大抵の作業ではない。だから、HPLの著作権は自分たちが持っている、というアーカム・ハウスのウソが長年に亘って通用し続けたと言えるわけだけど……)、HPLの著作の著作権が更新されていることを確認することはできない。そのため、HPLのほとんどの作品は既にパブリック・ドメインである――という結論が導き出されることになる。
では、なぜ更新手続が取られることがなかったのか? これが、はっきりしない。で、いろいろなことが言われているわけだけど、それを説明するためにも、そもそもアーカム・ハウスは何を根拠に自分たちこそは正当なHPLの著作権ホールダーだと言い張ってきたのかを確認しておく必要がある。これは、煎じ詰めるならば(HPLと著作権の問題を説明しようとすれば、何かと煎じ詰める必要がある)、2つの文書の存在に行きつく。1つはアーカム・ハウスの創設者であるオーガスト・ダーレスとドナルド・ワンドレイがHPLの2人の法定相続人(Ethel Phillips MorrishとEdna Lewis)と交わした文書。もう1つはHPLが常連寄稿者(掲載作品数は死後に掲載されたものを含め、全部で46編にも及ぶ)だった『ウィアード・テールズ』の出版元であるShort Stories, Inc.と交わした文書。これらはいずれもオーガスト・ダーレスとドナルド・ワンドレイを譲受人とする著作権の譲渡に関するもので、アーカム・ハウス側としてはこれら2つの文書を根拠に、自分たちこそはHPLの正当な著作権ホールダーである――とアピールしてきたということになる。しかし、HPLのほとんどの作品は著作権存続のために必要な更新手続が取られておらず、現在、パブリック・ドメインになっている――という事実を踏まえるなら、こうした彼らの主張のどこかにウソがあった、ということになる。で、これについて従来言われてきたのは、まず2人の法定相続人と交わした文書について言えば、そこに記されているのはオーガスト・ダーレスとドナルド・ワンドレイにこれまで通り自由にHPLの著作を出版していいということだけであって、著作権の譲渡まで含むものではないのではないか? ということ。確かに文書の内容は至ってシンプルなもので、著作権の譲渡については、明示的には何も記されていない。確かにこの文書を以て、自分たちこそは正当なHPLの著作権ホールダーだ、と言い張っていたとするなら、それはちょっとムリがある。ただ、彼らが切り札よろしく手札としていたもう1つの文書がある。それがShort Stories, Inc.と交わした文書で、これはHPLが『ウィアード・テールズ』に寄稿した46編の著作の著作権をオーガスト・ダーレスとドナルド・ワンドレイに譲渡する内容のものだった――とされるものの、実は文書の原本は残っていない(とされている。実際、Wikisouceにもこの文書は収録されていない)。従って全ては憶測の域を出ないのだけど、HPL研究の第一人者として知られるJ・S・ヨシは1996年に上梓したH. P. Lovecraft: A Lifeにおいて、HPLは1926年以降は再版権(second printing right)は自分の手元にキープするようになったとしており、1926年以降に『ウィアード・テールズ』に掲載された34編に関しては、そもそもShort Stories, Inc.は売却しうる権利を有していなかった、という仮説を披露。文書の原本が残っていない以上、あくまでも仮説に過ぎないのだけど、J・S・ヨシは、そういう可能性をうかがわせる「考慮すべき状況証拠(considerable circumstantial evidence)」があると主張(なお、ワタシはH. P. Lovecraft: A Lifeを自分では読んでおりません。以上はウィリアム・ジョーンズがかつて書いていたことの受け売りであります)。で、仮にこのJ・S・ヨシの仮説が正しいとするなら、それら34編の著作権は2人の法定相続人が持っていたということになる。つまり、アーカム・ハウスが切り札よろしく振りかざした2つの文書にもかかわらず、HPLの著作の著作権は2人の法定相続人が持っていたという可能性が出てくるわけで、そうなると著作権存続のために更新手続を取るべき責任も彼ら――というか、2人は女性なので、彼女たちにあった。しかし、彼女たちはそれを怠った――という仮説が導き出されることになる。
ただ、こうしたHPLと著作権をめぐる議論に一石を投じるウェブ記事が存在する。Chris J. Karrという、なんでも本職はIT技術者らしいのだけど、大学院在学中にこういうことに興味を持って、3年間かけて書き上げた。担当教授からは大いに称賛され、出版するよう勧められもした。で、本人もその気になって相当、努力したらしいのだけど、結局、引き受けてくれる出版社は見つからず。とはいえ、本人としては、内容には絶対の自信を持っている。このままボツにするのは忍びない。ということで、ウェブ記事として公開することにした――と、そういう経緯らしい。ハテ、これによく似た話がワタシのごく身近――ものすごーく身近――にもあったような……。ともあれ、そんな元大学院生が書いたThe Black Seas of Copyrightこそはその記事。過去の裁判記録(何の裁判記録かについては後ほど改めて)なども掘り起こした、確かに見事な内容のもので、HPLの著作権の問題に興味を持っているものにとっては必読じゃないかな? と全力でプッシュした上で――さて、この記事に記されたことを踏まえるならば、著作権存続のために必要な更新手続を怠ったのは、2人の法定相続人ではない。著作権存続のために必要な更新手続を怠ったのは――なんとオーガスト・ダーレスだったらしいのだ。どういうことか? まずこの記事を読んで驚かされるのは、これまで原本は残っていないとされていたShort Stories, Inc.と交わした文書は、残っていた。Chris J. Karrによれば、アーカム・ハウスは度々この文書を公開するよう求められてきたにもかかわらず、拒否してきた、という経緯があるようだ。それをChris J. Karrが入手し、The Black Seas of Copyrightの典拠資料として公開しているのだ。なんでも裁判資料として提出されたものとかで、これは大変なお手柄ですよ。これだけでもThe Black Seas of Copyrightを読む値打ちはあるというもの。さらに、件の文書(ASSIGNMENT OF COPYRIGHT)を読むと、実はアーカム・ハウスが言っていたことは正しかったことがわかる。そう、HPLが『ウィアード・テールズ』に寄稿した46編の著作の著作権は間違いなくオーガスト・ダーレスとドナルド・ワンドレイに譲渡されていたのだ。そのことが文面からハッキリと読み取れる。ちなみに、Chris J. Karrによれば、J・S・ヨシも現在はこの46編に関してH. P. Lovecraft: A Lifeで掲げた仮説を取り下げているらしい。そりゃあそうだよねえ、この文書を素直に読むならば、そういう解釈は出てくるはずがないもの。
しかし、こうしてアーカム・ハウスが、自分たちこそはHPLの正当な著作権ホールダーである、と主張する根拠としてきたもう1通の文書の内容が明らかとなり、それによって『ウィアード・テールズ』に掲載された46編の著作権に限れば間違いなくアーカム・ハウスが持っていた――ということになると、本来ならばそれら46編の著作権は現在も生きている――はず。だって、アーカム・ハウスがそれら46編の著作権の更新手続を怠るなんてことはまず考えられないので。しかし、なぜかCopyright Renewal Databaseで検索しても、それら46編の著作権が更新されているという事実は確認できない……。
さて、ここからがいよいよ本稿の本題。実はそれら46編の著作権が更新されている事実を確認できないのは、当然なのだ。なぜなら、それら46編の著作権は著作権存続のために必要な更新手続が取られておらず、既にパブリック・ドメインである――ということを、当のアーカム・ハウスの顧問弁護士が裁判の場でハッキリと証言しているのだから。この裁判、アーカム・ハウスとドナルド・ワンドレイとの間で争われたもので、実はドナルド・ワンドレイはオーガスト・ダーレスの死後、アーカム・ハウスを訴えているのだ。まずはこの裁判について簡単に説明するなら、オーガスト・ダーレスとドナルド・ワンドレイは、1955年、2人の内のどちらかが亡くなった時、残る1人がアーカム・ハウスが所有するHPLの全ての著作権とそれから得られるロイヤルティーを引き継ぐという文書に署名していてた(この文書もChris J. Karrのウェブサイトで公開されていて。それがコチラ)。そして、1971年7月4日、オーガスト・ダーレスは長い闘病の末、亡くなることになるわけだけれど、件の文書に従えば、これによりアーカム・ハウスが所有するHPLの全ての著作権とそれらから得られるロイヤルティーはドナルド・ワンドレイが引き継ぐことになるはずだった。ところが――オーガスト・ダーレスの死後、アーカム・ハウスの利益を代弁する立場となった顧問弁護士のForrest D. Hartmannはこれを拒否したのだ(つーか、おそらくは拒否するしかなかったんだろう。コトの次第がわかってみれば……)。かくてオーガスト・ダーレスが亡くなった2年後の1973年、ドナルド・ワンドレイはかつて自らも立ち上げに参加したアーカム・ハウスを訴えるという事態に――。
さて、こうして、かつての〝盟友〟であるオーガスト・ダーレス(の代理人)とドナルド・ワンドレイが争うという、なんともやるせないと言えばやるせない、しかし一方でさもありなんと思わせられるような(なにしろ、あの国のことですからねえ)裁判が開始されたわけだけれど、ほどなく両者は法廷で対決することになった。そして、それぞれの言い分を宣誓供述というかたちで明らかにすることとなったのだけど、その際、意外過ぎるくらい意外な事実がForrest D. Hartmannによって明かされることになる。なんとアーカム・ハウスが持っているはずだった46編の著作権は著作権存続のための更新手続が行われていないので既にパブリック・ドメインだというのだ。まずは1974年5月23日に行なった証言で述べたところによれば――
Insofar as the copyrights are concerned, I can testify that there are no renewal copyrights for any of the H.P. Lovecraft stories that were signed on October 9, 1947 to August Derleth and Donald Wandrei.
またこの件に関しては1974年5月24日付けの申立書でも次のように触れられているという――
The forty-six (46) Lovecraft stories contained in Exhibit "B" were not renewed by the assignees nor could they do so under the copyright law. Thus all of the stories are now in the public domain with the result that there are no rights contained or effective under the agreement between Donald Wandrei and August Derleth, dated November 8, 1955.
件の46編の著作権は譲受人(assignees)によって更新されておらず、既にパブリック・ドメインである――。ね、これじゃあ、そもそもドナルド・ワンドレイと交わした約束なんて履行しようがなかったんだ……。しかし、これはどういうことなんだろう? なぜアーカム・ハウスは――というか、ドナルド・ワンドレイはこの件を知らなかったようなので、ここはオーガスト・ダーレスは、と言い換えるべきか――自分たちが正当なかたちで手に入れた権利の存続手続を取らなかったのだろう? 所詮、アーカム・ハウスというのは、適切な著作権管理もできない、アマチュア・プレスに毛の生えた程度の出版社だった、ということになるのだろうか? ただ、それはちょっとねえ。というのも、Copyright Renewal Databaseで検索すると、アーカム・ハウスから刊行されたHPLの著作に関係する著作権が多数ヒットする。これらは「編集著作権」と呼ばれるもので、アメリカ著作権法では作品集などの場合、収録されている個々の作品とは別に著作権が認められている。他にも原作から派生した「二次的著作物」とか複数の作家の作品によって編まれたアンソロジー(「集合著作物」)などもすべて別個に著作権が認められており、これらは総称して「編集著作物又は二次的著作物における著作権」と定義されている。Copyright Renewal DatabaseでヒットするHPLの著作に関係する著作権というのは、この「編集著作物又は二次的著作物における著作権」(現在、刊行されているHPLの著作の前付けにもしアーカム・ハウスないしはオーガスト・ダーレスの名前が著作権者として記されているなら、それもこの「編集著作物又は二次的著作物における著作権」の保有者として)。そしてアーカム・ハウスはこれら「編集著作物又は二次的著作物における著作権」についてはきっちりと更新手続を行なっているのだ。にもかかわらず彼らは肝心要のHPLの著作権の更新は行なわなかった――ということになる。これは不思議ですよ。
さらに不思議なのは、ワンドレイがアーカム・ハウスを訴えたこの裁判それ自体。ワンドレイはダーレスと生前に交わした約束に従い、アーカム・ハウスが所有するHPLの著作の著作権とそれから得られるロイヤルティーを引き渡すようアーカム・ハウスに求めたわけだけれど、ところがその裁判でHPLの著作の著作権が著作権存続のために必要な更新手続が取られていなかったことが明らかになるというサプライズ。ということはですよ、ワンドレイはアーカム・ハウスが――というか、オーガスト・ダーレスが――著作権の更新手続を取っていなかったことを知らなかったということになる。当然、彼としては著作権存続のために必要な手続は取られているという考えだったのだろう。だからこそ、アーカム・ハウスを訴えた。ということは――だ、アーカム・ハウスが著作権の更新を行なわなかったのは、偏にオーガスト・ダーレスの判断だった、ということになる。
では、なぜダーレスは著作権の更新を行なわなかったのか? これについて、Chris J. Karrは何も記していない。そもそもそういう方向に彼の興味は向かっていないようだ。しかし、これは非常に重要な論点ですよ。だって、正にこの判断によって、HPLが『ウィアード・テールズ』に寄稿した46編は、今日、パブリック・ドメインとなっているのだから。そうした結果をもたらした判断に興味が向かうのは当然。では、なぜオーガスト・ダーレスはそれら46編の著作権の更新を行なわなかったのか? まず考えられるのは――「更新権」がネックとなったという可能性。多分、著作権に詳しい人でも、この「更新権」について知っている人はそうはいないのでは? かく言うワタシはかつて(ペーパーバック屋だった頃)、著作権について相当勉強した時期がありまして(その一端については「ペーパーバックの倉庫から③」をお読みいただければ)、この「更新権」についてもその頃に学んだものだけれど――実はアメリカ著作権法では、著作権の更新を行なえる「更新権」は著作権とは別に定められていて(あるいは、定められていた。現在は同趣旨の「終了権」に姿を変えているものの、基本的な考え方はそのまま引き継がれている)、当然のことながら著作者に与えられている。ここはワタシなんかが説明するよりも、しかるべき専門家の説明を引いた方がいいでしょう。ということで、当時、ワタシがテキストとした安藤和弘「アメリカ著作権法における終了権制度の一考察:著作者に契約のチャンスは2度必要か」(『早稲田法学会誌』58巻2号)より、この権利を理解するために必要な要点部分を書き出せば――
アメリカ著作権法は、最初の連邦著作権法の1790年法から現行法の1976年法に至るまで、一貫して著作者に対し、作品の正当な価値に見合った報酬を受け取る2度目のチャンスを与えてきた。この法制度は、1790年法の更新制度から1976年法の終了権制度へと変化を遂げるが、製作者による搾取から交渉力の弱い著作者を保護するという崇高な立法趣旨はいささかも変わっていない。このような法制度が200年以上にわたり堅持されているという事実は、アメリカ法に対し、冒頭のような先入観を持つ者にとっては驚きであろう。
(略)
このように紆余曲折のあった法改正であったが、結局、1909年法は、著作権の保護期間を28年、更新による延長期間を28年とした。同法により、最初の保護期間の28年目に著作者が更新手続を行えば、第三者に著作権が譲渡されていても、著作権は自動的に著作者に復帰する。また、著作者がライセンスを付与しても、更新をもって契約は自動的に終了する。更新手続がなされなかった場合、著作権は公有に帰すことになる。
連邦議会は、更新制度によって、2つの目的を達成しようとした。第1は、著作者または遺族に対し、作品から得られる正当な利益を得る2度目の機会を与えることである。著作者は、多くの場合、出版社との契約において、交渉上、弱い立場に置かれるものであり、経済的に不利な契約を締結せざるを得ない。さらに作品の価値は市場が決めるものであり、契約交渉の時点では、その価値が分からないため、報酬に作品の価値が正確に反映されていない。連邦議会は、このような事情を考慮し、更新制度というシステムを作ることによって、しばしば出版社から不当に搾取される作家や家族を保護しようとしたのである。
第2の目的は、権利者が著作権法による保護を望まない場合、最初の保護期間の経過後に権利を失効させることである。著作権は、著作物の利用の独占を許すものであり、公正な競争を前提とする資本主義の原則からすると、権利の存続を最小限に抑えたい。この観点から見ると、権利者が権利の存続を欲しないものを法律で保護して独占を認める必要はないということになる。権利保護の必要のない著作物は28年で保護を終了し、パブリック・ドメインにすることがもう一つの目的である。
アメリカ法に対し、冒頭のような先入観を持つ者にとっては驚きであろう――とは、アメリカ著作権法が「レコード会社や映画会社、出版社のメディア側の製作者を厚遇していると言われている」ことを指しているんだけど、確かにねえ。よもやアメリカ著作権法に「製作者による搾取から交渉力の弱い著作者を保護するという崇高な立法趣旨」があったとは……。ともあれ、「最初の保護期間の28年目に著作者が更新手続を行えば、第三者に著作権が譲渡されていても、著作権は自動的に著作者に復帰する」――というのは、いささか〝目から鱗〟というか。著作権の更新にそういう権能があったとは、この論文を読むまでは思いもしなかったこと。著作権の更新とは単純に著作権の保護期間を延長するためのものだと思っておりましたので。しかし、↑の解説を踏まえるならば、むしろ著作権の更新とは著作権が置かれた状況をリセットするための手続ということになる。そして、それは「製作者による搾取から交渉力の弱い著作者を保護するという崇高な立法趣旨」から生れてきたものということになるのだけれど――ただし、必ずしも実態は法の趣旨に沿っていたとは言えないようで、実際には「更新権の売却」も横行していたとか。「出版社は経済的に困窮する著作者に対し、最初の保護期間だけでなく、更新期間の著作権をも安い報酬で譲り渡すように迫り、多くの著作者がこれに応じた」――なんてこともこの論文には記されている。つまり、「製作者による搾取から交渉力の弱い著作者を保護するという崇高な立法趣旨」は現実の著作権ビジネスの前ではいささか無力だったということだね。ただ、まあ、ここではそういうことを論じるのが目的ではない。目的は、この「更新権」のもう1つの意外な側面を紹介すること。その意外な側面とは――
……更新権は、著作者が更新を申請できる時点まで生存した場合にのみ著作者に生じ、更新時に著作者が生存していない場合は、配偶者、子、孫、遺言執行者、直近親族などの法定の更新権相続人に帰属する権利である。したがって、著作者が更新期間の著作権を譲渡しても、更新期間が到来する前に死亡してしまうと、更新権は法定の更新権相続人に相続され、著作者との契約に関わらず、譲受人は更新期間の著作権を取得することができなくなる。
なんと「更新権」は、更新のタイミングで著作者が死亡していた場合、「配偶者、子、孫、遺言執行者、直近親族などの法定の更新権相続人」の手に渡るという仕組みになっているのだ。そのため、仮に著作者の生前に「更新権の売却」が行われていたとしても、譲受人は「更新権」の行使をできないのだ。行使するためには、別途、「更新権相続人」と交渉する必要がある――。HPLは1937年に亡くなっているわけだから、当然のことながら、オーガスト・ダーレスとドナルド・ワンドレイが『ウィアード・テールズ』の出版元であるShort Stories, Inc.から譲渡された46編の著作権の「更新権」は2人の法定相続人の手に渡っていた。しかし、彼らと2人の法定相続人の間で「更新権」の譲渡が行われたことを裏付ける文書は存在しない。また、オーガスト・ダーレスもそのようなことは主張していない。つまり、彼(ら)には件の46編の著作権を更新することはできなかったのだ……。
どう? なぜオーガスト・ダーレスは著作権の更新を行なわなかったのか? という問に対する相当に説得力のある解と評価していただけるのでは? いやー、当時、一生懸命、著作権の勉強をした甲斐がったというもんだ――と、そうひとり悦に入りたいところではあるんだけど……ただ、自分で書いておいてなんなんですけどね、ワタシとしては、この説は採用したくない(え?)。というか、これで納得したんじゃあまりにも多くの謎が未解決のまま残されるじゃないか。なんでオーガスト・ダーレスはアーカム・ハウスが著作権を持っているかのようにふるまい続けたのか? とか、なんでそのウソがバレたのに裁判沙汰になることがなかったのか? とか。これら重大な謎にとっては何の解決にもなりゃあしない(いや、それはそうだけど……)。
ということで、ここは全く別のシナリオを検討してみることにする。実は、かなりアクロバチックではあるのだけれど、これらの謎に一定の解を提供しうる全く別のシナリオがあるのだ。それは、オーガスト・ダーレスが件の46編の著作権の更新を行なわなかったのは「更新権」の問題からではなく(この問題は解決しようと思えば解決できた、と考える。ダーレスはHPLの2人の法定相続人とは良好な関係を築けていたのだから、「更新権」の問題についても話し合いで解決できたと考えた方が合理的)、全く別の理由から、あえて更新を行なわなかった――というシナリオ。どういうことか? まず、彼がHPLの著作権の保有を執拗に主張しつづけたのは、それによって高額なロイヤルティーを得ようという目的からではなく、HPLの著作の不正な使用を防ぐというのが第一の目的だった、と考えてみる。実際、昨今ではネットで検索しても全く情報を得られないような正体不明の出版社がHPLの作品集と称するものを出している出している。世に〝スパム出版〟なる言葉が存在するユエン。こうしたことは、アーカム・ハウスがHPLの著作権を保有していると信じられている間は(あるいはこれは、オーガスト・ダーレスが生きている間は、と言い換えてもいい)起こらなかった。正にHPLの著作は著作権によって守られていたのだ。しかし、そんな彼がなぜか著作権存続のために必要な更新手続を怠った。それは、彼が著作権なるものの負の側面についても十分に認識していたからではないか? 確かに著作権は薬にもなれば毒にもなる。むしろ最近は毒の方が強まっているのは否定すべくもない(なんですか、あの、音楽教室からも楽曲使用料を取り立てるという、JASRACの方針は……)。そんな毒が、なまじ著作権が存続しているがためにHPLの著作に回ってこないとも限らない。HPLの著作の正当な利用が阻害される、それによって「クトゥルー神話」の発展の妨げになるような事態――。そうした事態は、オーガスト・ダーレスが生きているうちは起こりようがなかった。しかし、彼の死後はどうか? それは誰にもわからない。仮に彼の管理下にあったHPLの全著作(それは実質的には『ウィアード・テールズ』に掲載された46編のみだったと考えるべき。しかし、彼はあかたもHPLの全著作が彼の管理下にあるかのごとくにふるまい続けた。彼の管理下にあるのがHPLの全著作である必要があったのだ)の著作権が適正に更新され、彼が亡くなった時点でも生きていたとするなら、それらはまずドナルド・ワンドレイの手に渡ることになる。しかし、ドナルド・ワンドレイが亡くなった後は? それは、全くわからない。また、ドナルド・ワンドレイがそれらをどう扱うかも全くの未知数。ことによるとそれらは営利を目的とする何ものかの手に渡るということだって、十分に考えられる。欲しがる出版社はどれだけでもあるだろうからね。むしろ、ワタシにはそうしたものたちの手に落ちない可能性を想像する方が夢想的であるように思える。もしかしたらオーガスト・ダーレスはそういう事態を危惧したのではないか? そして、自らの管理下にある46編を著作権が存続したかたちで遺すことを避けた。言うならばだ、上掲論文が挙げる「更新権」の第2の目的を実行したというかたちだね。即ち「権利保護の必要のない著作物は28年で保護を終了し、パブリック・ドメインにする」――、むしろその方がそれら46編を守ることに寄与する……。
こういう仮説――ま、妄想ということでもいいけどね――を想定するならば、なぜForrest D. Hartmannの爆弾証言によってそれまでアーカム・ハウスが言っていたことがウソだとバレたにもかかわらず、アーカム・ハウスないしはオーガスト・ダーレスが著作権詐欺に問われることがなかったのか? という謎に対しても1つの有力な解を提示し得る。それは、アーカム・ハウスは許諾に当ってロイヤルティーの支払いを請求していなかったから――。オーガスト・ダーレスが声高に著作権の保有を主張しつづけたのはあくまでもHPLの著作を守るためであり、それによってロイヤルティーを得ることが目的ではなかった――と考えるなら、許諾に当ってロイヤルティーの支払いを請求しなかったという、いささか夢物語みたいなことだって考えられないことはない。てゆーか、そうとでも考えなければ、これほど明白な著作権詐欺が罪に問われることがなかった、という摩訶不思議な現実を説明できないんだよ……。
About Me
On PW_PLUS
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②
- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜
- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜
- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜
