カトリーヌ・リュシエール著『恋人の秘密』
〜フランス書院の海外ポルノ小説シリーズを読む③〜
中田耕治の公式サイト「中田耕治ドットコム」で読める「中田耕治のコージートーク」は2005年12月17日から始まって(ただし、この時点で連載第153回とされているので、実際の開始はもっと前のはず)、何度かの休止期間を挟みつつ、最終的には亡くなる5日前の2021年11月21日まで継続。さらにその後も連載中だった「少年時代」が管理人によって続行され(原稿自体は既に完成しており、管理人に渡されていたという)、2022年3月14日付けで「完」となっている。まあ、最後は本来の意味のブログではなくなっていたわけだけれど、でも「中田耕治のコージートーク」というタイトルには適っていたとは言えるのかな。「少年時代」にしても、なかなかに寛いだ(「コージー」な)スタイルで綴られているのは間違いない――かつて『血と薔薇』に「ド・ブランヴィリエ侯爵夫人」を寄稿した頃に比べればね。ただ、当初の純然たるブログだった頃には読者からのメールが紹介されたり(その中には中田耕治のハードボイルド小説の熱心な読者という人物からの「いまからでも遅くはない。ハードボイルド・ミステリーを書け!」というリクエストに対して、「少し前だったら、私もグラッときたかも知れない。/そろそろ何かあたらしいことをやってみようか、と思いはじめていたから。/しかし、今のところ、とてもミステリーを書く気力も、体力もない。いや、もうミステリーを書く才能がない、というべきだろう」――と回答するなど、ワタシのようなモノにとってもなかなかに興味深いやりとりも含まれている)、311当時の率直な感情表現に接することができたり――と、「中田耕治」という人間を知るに当たってはより貴重なものであるという気はするなあ。中田氏が亡くなった今となっては、なおのこと……。
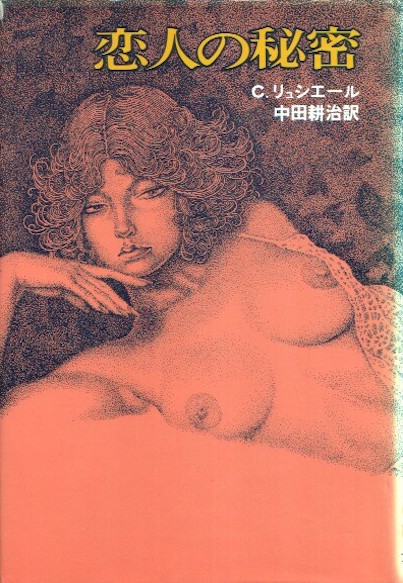
ということで、『恋人の秘密』である。実は「中田耕治のコージートーク」に本作についての記載がある。まず「中田耕治のコージートーク」は最後は本来の意味でのブログではなくなっていたわけだけれど、そうした変化が顕著になったのは2018年からで、4月27日からは「ダニエル・ダリュー」と題する連載が3回ばかり。さらに5月25日からは「原民喜」と題する連載が始まって、これは全6回。そして6月28日からは何の前触れも説明もなく「1977年日記」の連載が始まっている。実はこれに先立つこと4年前の2013年8月17日付け記事で書庫を整理していたら1977年の日記が出てきたことが記されており、以後も6回ばかりこの日記を元にした記事がつづく。そして、その最後となった8月31日付け記事の最後で「さて、残りはすぐに焼き捨てよう」。しかし、そこまでハードボイルド(?)になれなかったというわけか、日記は〝焚書〟を免れていたと、そういうことになるようだ(なお、ついでに書いておくなら、中田氏は2007年1月14日付け記事でこんなことを書いている――「当時、長編を一つ書いた。「川崎 隆」もの。500枚。しかし、どこからも出せなかったので、えいっとばかり、焼き捨てた。どうせたいした作品ではない。この事情は、ある編集者が知っている」。しかし、1977年の日記も「すぐに焼き捨てよう」と書いていたのに残されていたことを思えば、この川崎隆もの500枚も書庫のどこかに眠っている可能性も……?)。かくて2018年6月28日からは「1977年日記」の連載が始まるわけだけれど、1977年といえばちょうど『恋人の秘密』が刊行された年。当然のことながらと言うべきか、本作についての記載もあるのだ。たとえば、7月14日付けで――
「三笠書房」の三谷君に「カトリ-ヌ」の原稿を。「日経」の青柳君に原稿をわたした。
『恋人の秘密』巻末の「訳者あとがき」によれば、本作の担当編集者は三谷喜三夫氏。従って「「三笠書房」の三谷君」とはフランス書院(三笠書房の完全子会社)の三谷喜三夫氏のことであり、「カトリ-ヌ」とは本作を指すという理解で間違いない。さらに「カトリ-ヌ」については7月19日付け記事でも言及がある。これがなかなかに興味深い――
午後2時半。新橋、「ア-トコ-ヒ-」で、「二見」の三谷君に、「カトリ-ヌ」の最後の原稿をわたす。
この作品には、私の・・が隠されている。
まず、「「二見」の三谷君」というのは「「三笠」の三谷君」の間違いでしょう(日記には二見書房の「長谷川君」という人物の名も頻出する。調べたところ、1978年には中田氏の訳でステファン・ルイス著『家出娘』が二見書房の「ロマン・ダムール」シリーズの1冊として刊行されている)。その上で「カトリ-ヌ」について「この作品には、私の・・が隠されている」。なんとも意味深。隠されているものって、ナニ……? で、ワタシとしては、この1行を見つけられただけでも「1977年日記」を通読した価値はあったというものなんだけれど、日記には実はもう一回、本作への言及がある。ワタシの立場から言えば、これもなかなかに興趣をそそられるというか……。それは、8月9日付けのこんな記載なんだけれど――
「ミレイユ」続編の校正は、上野の駅の構内で赤を入れた。約束の時間ぎりぎりに石本がきてくれたので、「二見」に届けてもらうことにした。
冒頭の「ミレイユ」というのは本作に先立ってやはりカトリーヌ・リュシエール著としてフランス書院から刊行された『秘戯』(原題はMireille)のことで、「「ミレイユ」続編」とは、だから本作を指している。そうなると、その後の「二見」は「三笠」の間違いということになるわけだけれど――ともあれ、中田耕治は本作の著者校正を上野駅の構内で行っていたということ。で、なんでそんなことにワタシが興趣をそそられるかと言えば――実は、この時、中田耕治は富山に向かうために上野駅にいたのだ。それは↑の下りにつづく部分を読めばわかる――
「ミレイユ」続編の校正は、上野の駅の構内で赤を入れた。約束の時間ぎりぎりに石本がきてくれたので、「二見」に届けてもらうことにした。
プラットフォ-ムを走った。やっと飛び乗ったとき、みんなが歓声をあげた。
すべり込み、セ-フ。
「先生は時間に間に会わなくても、きっとあとからひとりで登ってくる、と思っていました」
という。
メンバ-は――安東夫妻、吉沢 正英、工藤 淳子、石井 秀明、はじめて参加した甲谷君。今回は、「中田チ-ム」の最強のメンバ-。
すぐに眠ることにした。睡眠不足なので。
早朝。富山から立山線で、有峰口。
ここからバスで折立まで。
さすがに登山者が多い。
私は、車中で、よく眠れなかったため、ひょっとすると、おもしろくない山行になるかも知れない、と覚悟をきめた。セ-タ-は着ない。
おわかりですよね。この時、中田耕治は富山県富山市有峰の折立から入って北アルプスを縦走する山行のために上野駅にいたのだ。そして、その上野駅でぎりぎりまで粘って『恋人の秘密』の校正を行っていたということになる。それにしても、よくもまあこんな凄まじい小説の校正を、登山客や何やでごった返す上野駅の構内でねえ。しかも、ぎりぎりで夜行列車に飛び乗った中田氏は翌日には北アルプスを縦走してるのだ。すごい体力ですよ。おそらくはこの体力があってこそのあの凄まじい性描写なんだろう……。なお、『恋人の秘密』巻末の「訳者あとがき」にもこうした消息を伝える記載がある。曰く「この夏、私は八ガ岳や、黒部五郎、三俣蓮華、双六岳と、山にばかり登っていて、原稿の完成が遅れたため、三谷君を悩ませましたが、ここにお詫びと、あらためて感謝をささげます」。ここに名前の挙がる黒部五郎、三俣蓮華、双六岳というのがこの時の山行で踏破した山ということになる。いずれにしても、上野から富山へ。そして、レ・ザルク(第1部「山荘の夜」の舞台)へ――と、そういうことになるのかな?
で、「中田耕治のコージートーク」で読める「1977年日記」で本作に言及されているのは以上の3か所ということになるわけだけれど、『恋人の秘密』という小説について考える上で重要なのはやっぱり7月19日付け記事の記載だよね。そう、「この作品には、私の・・が隠されている」という下りね。この「・・」って、ナニ? まあ、それがわかれば苦労しないわけで……。ただ、『恋人の秘密』という小説は『恋人の秘密』というタイトルではあるんだけれど、特段、ヒロイン(パリのブルジョワ娘・ミレイユ。二十歳。実業家として知られる父はさる女優を後援しており、それに反発したミレイユは「リュー・アルベール・トマの安アパルトマンの一室を借りて一人で生活している」という設定)には「秘密」と言えるようなものはないんだよね。つーか、本作でミレイユは二十歳という年齢にしてはちょっとありえないような凄まじい性体験を繰り広げることになるわけだけれど、一方で意外と貞淑(という用語の選択が適切なのかどうかは別として)なんだよね。ここはまずその凄まじいばかりの性体験を『恋人の秘密』だけではなく前作の『秘戯』から順を追って紹介するなら――自慰→クンリニングス→初体験→同性愛→3P(女2男1)→3P(女1男2)→スワッピング→緊縛(と同時にこのエピソードは黒人との「異人種間性交」でもある)→乱交(最終的にはアナル・セックスに発展する)――ということになる。もうね、性の〝秘戯〟のフルコースと言っていいでしょう。しかもですね、特筆すべきはこれはわずか半年の間の出来事なのだ。半年で密かに自慰に耽っていた幼気な少女が乱交パーティーに参加し、あろうことかアナル・セックスまで経験するに至るというね。いやー、凄まじい。ただ、そんな野放図とも言える性の冒険にあって、唯一、救いとなるのは(なーんて、いかにワタシがこのテの世界に不慣れかということではありますが……)ミレイユは誰彼かまわず性交渉を行っているわけではないということ。3Pもスワッピングも乱交もその時々の恋人(『秘戯』の時点ではジャン・ポール、『恋人の秘密』の時点ではフィリップ)とともに参加しているんだよね。たとえば、3P(女1男2)の場合は――
フィリップが笑い出した。「ミレイユはすばらしいだろう。ロベール?」彼はシャツのボタンを外しはじめた。
「きみは……これでも怒らないのか?」ロベールは動揺をむき出しにしていた。ミレイユから離れようとしても、ミレイユは両腿をひきしめて彼を放そうとしなかった。彼がミレイユと性交していることは見ただけでわかる。それなのに、フィリップは咎めようともしないし、罵しるわけでもない。「気にならないのか、フィリップ?」
「ああ、気にならないさ」フィリップがこともなげにいった。「すばらしいじゃないか――ぼくがいちばん好きな二人がお互いにいつくしみあっている。さあ、つづけろよ、ロベール。ミレイユをじらさないで。たっぷり味わわせてやってくれ。ミレイユはきみを完全に行かせたがっているよ、そうだろう、ミレイユ?」
「そうよ」ミレイユが低い声で恥ずかしそうにいった。「とてもすばらしいからだをしているの、ロベールが。あたしにぴったりだわ。ねえ、ロベール? やっぱりあたしのいったとおりよ」
「信じられないなあ!」ロベールはつぶやいた。ひどい動揺のなかで、自分の緊張した部分が少しずつ萎えてゆくような気がする。フィリップも緊張していることがわかった。そのため、フィリップの昂奮している表情や、あわただしく下着をとった動作に、ロベールは安堵と同時に、いっそう動揺も募ってきた。
「信じろよ」フィリップがいった。「楽しくやればいいさ。これは、はじめから予定の行動だった。ミレイユが、ぼくときみ二人に愛して欲しいといい出してね」
「まさか!」
「少し頭がおかしいんだよ、ミレイユは」フィリップのものがりゅうりゅうと屹立していた。
「ぼくは賛成したんだ。きみだって、もう引き返せないだろう? ミレイユを共有することに異議はあるかい?」
「そりゃあ、ないさ」
フィリップはシャツを脱いだ。「食事中、ミレイユはきみを誘惑しようとしていた。あれで、きみも昂奮したろう?」
ミレイユが腿を開いたので、ロベールはミレイユの顔を凝視していたが、ミレイユが締めつけてくるのを感じて、またはげしく動きはじめた。「そういうことだったのか、ミレイユ? それならそれでいいさ」これまでのようにフィリップのことを気にしないですむために、動きが大きく、つよいものになると、ミレイユの声もあたりを憚からないものになった。たちまちミレイユは大きな陶酔に捲き込まれた。ミレイユはつぎつぎに声をあげた。
「すばらしいわ! 二人の恋人たち。フィル、きて。ロベールがファックしているうちにキスして」
恋人ともども参加しているわけだから、もとより2人の間に「秘密」なんてあろうはずもない。それでいて小説のタイトルは『恋人の秘密』なのだ。これって、どーゆーこと? ということになるわだけれど……実は『恋人の秘密』には確かに1つの「秘密」があるのだ。それはオーサーシップにまつわる「秘密」。「ハードボイルドの向う側〜フランス書院の海外ポルノ小説シリーズ〜」にも書いたように、中田耕治は『秘戯』の「訳者あとがき」で著者とされているカトリーヌ・リュシエールについてこんなふうに紹介しているのだけれど――「この作家について、簡単に紹介しておきます。まだ二十代の若い作家ですが、外国の女流作家の通例で生年月日を発表していません。彼女の存在を知ったのは一九七二年でしたが、翌年四月二十八日、東京で逢って親しくなりました。この日、お茶の水の付近の喫茶店で逢って、いろいろ話をしたあと、たまたま封切られていた「陽は昇り陽は沈む」という映画を見て、夜は山ノ上ホテルでてんぷらを御馳走したことをおぼえています」。しかし、かくも具体的なエピソードを伴って紹介されているカトリーヌ・リュシエール(Catherine Luchair)なる作家についてGoogleにお伺いを立ててみてもヒットするのは「翻訳作品集成」(雨宮孝氏が個人で運営されている翻訳作品の書誌情報を網羅したデータベース。ワタシはペーパーバック屋だった頃からお世話になっております。ここは改めてその尽力に敬意を表するものであります。MISDASにしてもそうだけれど、簡単にできるものじゃないですよ。今の御時世、いろんな「収益化」の手管があるようだけれど、こういう地道に運営されているサイトこそ本来は「収益化」の恩恵に与るべきではないのかと……)の本書に関するデータのみなんだよね。要するに「カトリーヌ・リュシエール」なる作家はフランス書院の海外ポルノ小説シリーズに収録された2作品の著者としてしかこの世に存在しないということ。これはねえ、何か「秘密」が隠されていると言わざるを得ず……。ということで、「ハードボイルドの向う側〜フランス書院の海外ポルノ小説シリーズ〜」でも書いたように、小鷹信光が翻訳を装った創作であることを認めているチャールズ・バートン著『女主人』同様、カトリーヌ・リュシエール著とされる2作も実際は中田耕治の創作である可能性が見えてくるわけだけれど、「1977年日記」の7月19日付け記事に記された「この作品には、私の・・が隠されている」という〝告白〟は、事実上、それを認めたものと言えるのでは? その場合、「・・」に入るのは「秘密」かな? つまり「この作品には、私の秘密が隠されている」。ちなみに、中田耕治は「中田耕治のコージートーク」の2007年1月14日付け記事(例の川崎隆ものについて記した記事)でこんなことも書いている――「ミステリーを書かなくなったのは、『メディチ家の人びと』を書いてからだった。それまでは、パルプ・マガジンにミステリーからポルノまで書きとばして、ルネサンス関係の資料を買ったものだが、『メディチ家』を出したとたんに、どこからも注文がこなくなった。これにも驚いた。つまらないミステリー、ポルノを書きとばしている大学の先生が、ルネサンスの研究をしていると知って敬遠したらしい」。だからね、中田耕治はポルノを「書いていた」わけですよ。そういうことを、遺された日記の中で認めていた――と、そういうことになるわけで……。
本稿は『恋人の秘密』の「秘密」に焦点を当てたものなので本文での言及は控えざるを得なかったのだけれど、実はカトリーヌ・リュシエール名義の第1作『秘戯』に、これは、と唸った一節がある。中田耕治のポルノ小説について書く、なんてことはそうそうあることではないだろうし、いつなにがあるかわからないご時世でもあるようなので、やっぱり書けるときに書いておいた方がいいでしょう。ということで、それはこんな下りなんだけれど――
「ミレイユ、オシッコさせて」シルヴィーがはっきりした声でいった。
ジュリアンはすぐに、
「ぼくがやるよ」
といったが、シルヴィーはミレイユをまっすぐ見ながら、落ちついた声でいった。
「ミレイユの仕事よ、これは」
「いいわ、あたしにさせて」
ミレイユはベッドの下から溲瓶をとった。ジュリアンが外に出ようとすると、
「そこで見ていて頂戴、ジュリアン」
と、シルヴィーがいった。ミレイユは、自分を侮辱するために、いやがらせのためにわざとそういうことをさせるとしか思えないシルヴィーに嫌悪を感じたが、シルヴィーのほうは無感動にちらとミレイユを見ただけだった。ミレイユがカヴァーの下に溲瓶をさしこむと、
「しっかりあてて頂戴。こぼれないように見ているのよ」
シルヴィーがいった。ミレイユはシーツカヴァーを外し、祈るようにしてシルヴィーの下半身をむき出しにした。すっきり伸びた二本の足がゆっくり開いた。そこにシルヴィーのブリュネットのしげみが開かれた。かすかに動物のような匂いがして、ミレイユはそこに溲瓶の口を押しつけた。シルヴィーのわざとらしい露出趣味にたじろいではいけない、と思った。わざとやっているのだから、こちらも、いまさら驚くようなことじゃない、といったようすを見せてやるわ。ミレイユは祭壇につらなる巫女のように冷静にかまえていた。
「手で開くようにして」シルヴィーがいった。ミレイユがいわれたとおりにしたとき、シルヴィーが下から見あげているのがわかった。ミレイユはその眼をわざと無視した。ただ、ブリュネットに光って、ふっくりともりあがった丘にシルヴィーの手がふれたとき、いきなり液体がほとばしり出た。ミレイユはいそいで溲瓶をあてがった。ガラスにあたる液体の音がした。
「見ていてといったはずよ」
ミレイユの指がすっかり濡れていた。溲瓶をくるんだタオルで拭くと尿の匂いが鼻をついた。茶褐色の液体がたまりはじめ、少しずつ重みがましてくる。あたたかさが掌につたわってくる。ガラスを通して見ると、水がぶつかりあい、泡立ち、見たこともない不思議な流れを描いていた。やがて流れはやんだ。
ジュリアンが部屋を出て行った。彼は何も見ていなかったに違いない、とミレイユは思った。しかし、ガラスにあたる水の音楽ははっきり聞いたはずだった。ミレイユは、タオルでシルヴィーの濡れた性毛を拭いてやった。溲瓶をもって浴室に行った。その液体を流す前に眼の前にかざして見た。透きとおった茶褐色の水が揺れていた。いつか学校でやった化学の実験、酸性の溶液がアルカリ性に変化するときの、フェノールフタレイン溶液のあざやかな変化を彼女は思いうかべた。
ミレイユの友人であるシルヴィーが浴室で倒れて入院する事態に。見舞いに訪れたミレイユはシルヴィーに求められて排泄の世話をすることになったわけだけれど……その尿が溲瓶に溜まる様子や尿そのものの様がかくもピュアな筆致で……。ワタシ的には、この一節にめぐりあえただけでもカトリーヌ・リュシエールもの(という言い方をあえてしましょう)2冊を読んだ価値はあったというもの。中田氏にとってこの2冊はそれこそ「書きとばした」というようなシロモノなのかもしれないけれど、いやいやどうして、このカトリーヌ・リュシエールもの2冊は読むに値する紛うことなき「文学」ですよ――と、氏の遅れてきた信奉者としては……。
About Me
On PW_PLUS
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②
- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜
- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜
- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜
